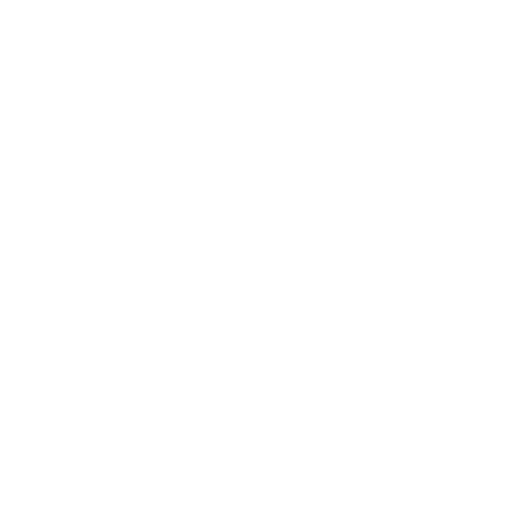青茶とは

豊かな風味と共に心地良い憩いの時間を提供する、青茶。しかし、その名称からイメージする一般的な日本茶や紅茶とは少し異なる存在です。青茶と聞いて、「一度は聞いたことがあるけれど、具体的には何だろう?」と思われる方も多いのではないでしょうか?ここでは、その青茶について、その歴史や特徴、美味しい淹れ方まで詳しく掘り下げてみましょう。
青茶の製造工程
青茶の製造は、以下の7つの工程で進められます。各工程が茶葉の風味や香りを引き出すために重要な役割を果たします。
摘採(てきさい)
茶葉を摘む工程で、手摘みと機械摘みがあります。
萎凋(いちょう)
茶葉を日光に当てて乾燥させ、香りを引き出す工程です。この際に軽く発酵が始まります。
揺青(ようちん)
茶葉を揺らして擦傷をつけることで、さらに酸化(発酵)を進めます。
殺青(さっせい)
加熱して酸化を止めます。この工程で青茶特有の水色や味が決まります。
揉捻(じゅうねん)
茶葉を丸くするか細長くするか形を整え、香りと味を最大限に引き出します。
乾燥
乾燥機で水分を除去し、水分量を5%以下に調整します。
焙煎
最終的に火を通して風味を整えます。焙煎の強弱により「重火」「中火」「軽火」と分類されます。

青茶の美味しい飲み方
青茶を楽しむ際には、中国の伝統的な「工夫茶」のような本格的な方法もありますが、ここでは日常的で簡単な淹れ方をご紹介します。
急須を温める
紫砂壺などの急須を熱湯で温めてから湯を捨てます。
茶葉を入れる
急須の底が隠れる程度の量の茶葉を入れます。
お湯を注ぐ
沸騰したお湯を注ぎ、1分間蒸らします(茶葉によって時間を調整します)。
茶器を温める
茶海や茶杯に熱湯を注いで温めます。
茶湯を注ぐ
急須から茶海に茶湯を移し、最後の一滴まで注ぎ切ってから各茶杯に分けます。
ポイントとして、なるべく高温(約100℃)で淹れることで香りが際立ちます。ただし、甘みを感じたい場合はやや低温で淹れるのも良い方法です。茶葉や茶器、水質などを調整しながら、自分好みの味を探る楽しさも魅力です。
青茶は日本人には馴染みの深いお茶?
青茶の中でも代表的なものが烏龍茶です。サントリーの「黒烏龍茶」をはじめとする製品で、多くの日本人に馴染みがあります。烏龍茶は中国茶の象徴的存在として知られており、「福建省産茶葉使用」という表記もよく見られます。この福建省は青茶の大産地であり、伝統的な製法と自然環境が高品質な青茶を生み出しています。
まとめ
青茶はその色から独特の風味を持つ伝統的なお茶で、長い歴史を持ちながら、その魅力や淹れ方がまだ広く知られていないかもしれません。しかし、その豊かで青々とした風味と適度な渋みは、あなたの一日を穏やかなひとときへと導きます。是非この機会に、青茶の美味しさを再発見してみてください。多様な日本のお茶文化の一環として、青茶の深淵を探求することは、お茶好きとしてのあなたの喜びを一層深めることでしょう。
よくある質問
青茶と烏龍茶の違いは何ですか?
青茶と烏龍茶は実質的に同じものを指しています。青茶は中国茶の分類上の正式名称であり、烏龍茶はその一般的な呼び名です。
両者の特徴は以下の通りです。
製法:半発酵茶として知られ、緑茶(不発酵)と紅茶(完全発酵)の中間に位置します。発酵度は約15%から70%まで幅広く、これにより多様な風味が生まれます。
味わい:緑茶の清らかさと紅茶の豊かさの中間的な特徴を持ち、茶葉によって様々な風味があります。
歴史:明代中期に福建省武夷山地区で誕生したとされ、その後、他の地域にも広がりました。
種類:発酵度や製法の違いにより、多種多様な青茶(烏龍茶)が存在します。代表的なものに武夷岩茶、安渓鉄観音、鳳凰単叢、台湾茶などがあります。
製造工程:主に摘採、萎凋、揺青、殺青、揉捻、乾燥、焙煎の工程を経て作られます。
特徴:花や果実を思わせる香りが特徴的で、世界中にファンがいます。また、茶葉の形状や色、水色の透明感なども品質の指標となります。
つまり、青茶と烏龍茶は同じお茶を指す異なる呼び方であり、その製法や特徴に違いはありません。