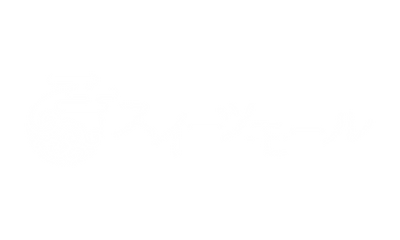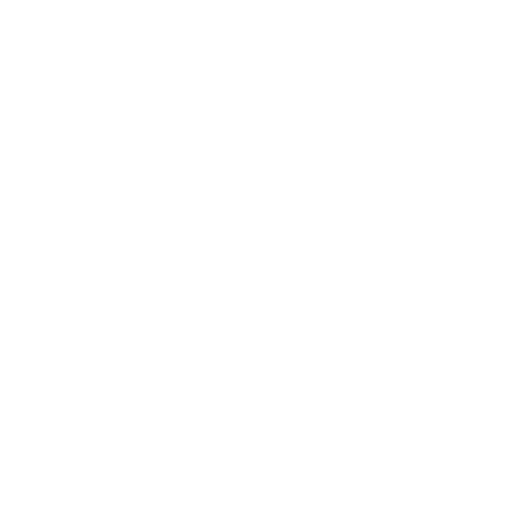イチョウがもたらす多様な恩恵

イチョウは木材としての用途はあまり一般的ではありませんが、その耐火性、耐大気汚染性、病害虫への強さといった特性から、街路樹、寺院や神社、学校などの景観樹として幅広く利用されています。非常に長寿であることでも知られ、数百年以上の樹齢を持つ「大銀杏」が多くの寺社で見られます。そして、秋の美味として親しまれるのが、その種子である銀杏(ぎんなん)です。銀杏の実が食べられる季節は、多くの人々に秋の訪れを告げる風物詩となっています。
建築・家具で評価されるイチョウ材の特長
イチョウ材は一般にはあまり知られていませんが、その細胞組織は針葉樹に似た構造を持っています。材は淡い黄白色を呈し、心材と辺材の色の区別はほとんど見られません。年輪の差が不明瞭でブナ材を思わせるほど緻密かつ均質な木質を持ち、柔らかく加工しやすいのが特徴です。肌目はきめ細かく、木目はまっすぐで、反り、ねじれ、割れ、収縮が少なく、形状の変化が起こりにくい優れた材です。気乾比重は約0.55と比較的軽く軟らかい部類に入り、耐久性はそれほど高くないとされています。しかし、器具、建具、家具、彫刻、カウンター天板、構造材、造作材、水回りなど幅広い用途で活用されており、特に碁盤や将棋盤にも適材とされます。ただし、音の響きがカヤ材に劣るため、その分野での評価は低めです。その他、昔は鶏肉を扱う店でまな板として重宝され、着物の裁ち板としても使われてきました。
景観と防災への貢献:植栽としての役割
イチョウは生育場所を選ばず、旺盛な萌芽力と病害虫への耐性、そして強い潮風にも耐える強さから、庭園、公園、街路、防風林、防火林など、非常に多様な目的で植栽されています。日本では、個人の庭や公園、そして寺社仏閣の境内に多く見られますが、大規模な森林としての造成はほとんどありません。特に古い社寺には、樹齢数百年を超える「大銀杏」と呼ばれる巨木が数多く存在し、訪れる人々の目を楽しませています。海外の植物園でもその姿はよく見られます。また、実生や挿し木によって盆栽としても人気があり、その美しい姿が愛されています。高木に成長するため一般の庭木としての利用は限られますが、成長が緩やかな「チチイチョウ」は庭木として採用されるケースもあります。
さらに、イチョウはその厚い樹皮がコルク質で気泡を多く含んでいるため、非常に優れた耐火性を持つとされ、防火目的の植林に活用されています。特に、明治神宮外苑のイチョウ並木は、関東大震災の際に火災の延焼を食い止めた実績があることから、都市の防災対策の一環として、街路樹にイチョウが積極的に採用されるきっかけになったと言われています。このイチョウの活用を提唱したのは、著名な造園家である本多静六氏であり、本多静六氏は、都市の防災対策としてイチョウの活用を提唱しました。
都市景観を彩る街路樹
イチョウは、その類まれな強靭さから都市環境に適した樹木として高く評価されています。病害虫に強く、塩害や大気汚染、さらには火災にも耐えうる特性を持つため、世界中の街路樹として広く親しまれています。特に秋には、鮮やかな黄金色に染まる「イチョウ紅葉」が都市の景観に華を添え、各地の並木道が多くの人々を魅了する風物詩となります。東京の明治神宮外苑や大阪の御堂筋といった、全国に名高いイチョウ並木はその象徴と言えるでしょう。御堂筋のイチョウ並木は1966年には樹齢およそ50年の木々が867本を数え、そのうち111本が雌株でした。雌株からは秋に種子、すなわち後述の銀杏が落ち、これが異臭を放つことがあるため、最近では街路樹として雄株のみを植栽する傾向にあります。また、イチョウはその生命力の強さから移植も容易で、たとえ大木であっても新たな場所に根付かせることが可能です。
日本各地の歴史を刻む巨樹・名木
日本の豊かな自然の中には、樹齢千年以上とも言われるイチョウの巨樹が数多く存在しています。これらの古木は、その悠久の時を刻む姿から、しばしば天然記念物として手厚く保護され、時には人々の信仰の対象として尊崇されてきました。特に印象的な例としては、日本最大級とされる青森県の北金ヶ沢のイチョウ、埼玉県飯能市の鳥居観音のイチョウ、東京都港区の善福寺のイチョウ、そして宮城県の苦竹のイチョウなどが挙げられ、それぞれが地域の歴史と文化を物語る存在となっています。
秋の味覚「銀杏(ぎんなん)」の魅力と安全な食べ方

イチョウが秋にもたらす恵み、それが通称「銀杏(ぎんなん)」と呼ばれる種子です。この硬い殻に包まれた内部の仁(さね、核)こそが、美味として珍重され、食用に供されます。一般には「銀杏の実」と表現されることもありますが、厳密には植物学上の果実ではなく、種子に分類されます。この銀杏を食用とする文化は、日本をはじめとする中国など、東アジア地域に特有の食習慣として根付いています。古くは1159年の中国の書物『紹興本草』にもその存在が記されており、さらに明代の『本草綱目』では鎮咳作用を持つ薬用としても利用されてきた歴史が紹介されています。まさに、古くから人々に親しまれてきた食材なのです。
銀杏(ぎんなん)とは?その正体と食用文化
銀杏の仁は、およそ直径1cmほどの紡錘形をしており、採れたての状態ではクロロフィル由来の鮮やかな緑色をしています。しかし、殻付きのままであっても常温で保存すると、比較的短期間で黄色へと変色してしまう性質があります。加熱することで再び透明感のある美しい緑色を取り戻しますが、さらに加熱を続けると、細胞内の酸性物質との化学反応により、クロロフィルからマグネシウムが失われ、黄褐色のフェオフィチンへと変化します。
この銀杏(ぎんなん)が最も美味しく食べれる旬の時期は、9月から11月頃の秋です。特に旬に先駆けて収穫される「走り銀杏」は、その名が示す通り、翡翠のような美しい緑色と、通常の銀杏よりも柔らかな食感、そして控えめな香りが特徴で、大変な高級品として珍重されています。日本料理では、茶碗蒸しや炊き込みご飯の彩りとして、また煮物や鍋物の具材、おひたし、串焼きなど、実に多様な形で「銀杏の実」が楽しまれています。その上品な風味は、お酒の肴としても格別です。東アジア圏では一般的な食材であり、韓国の屋台や居酒屋でも、香ばしく炒った銀杏が提供されています。また、水煮やオリーブ油漬けといった瓶詰や缶詰の加工品も流通しており、季節を問わず「銀杏の実」を手に入れることが可能です。ただし、銀杏には独特のほろ苦さがあり、外皮の部分には強い悪臭がある点には注意が必要です。
銀杏(ぎんなん)の下処理と調理法:食中毒のリスクと安全な食べ方
イチョウから実が落ちてきたら、まず独特の臭気を放つ外側の果肉(外種皮)を丁寧に取り除くことから始めます。この外種皮は素手で触るとかぶれる可能性があるため、ゴム手袋などを着用して作業し、その後きれいに水洗いしてしっかりと乾燥させることが肝心です。異臭の主な原因は、ウルシの成分と類似したギンゴール酸などのアルキルフェノール類で、これらが接触性皮膚炎を引き起こすことがあります。非常に甘く、糖度が30%に達することもありますが、生のまま食べるのは推奨されません。ただし、熱心な野食研究家の中には、丁寧に搾汁し煮詰めることで美味しく活用できると報告している例もあります。
殻付き銀杏の簡単な調理法(電子レンジ・フライパン)
殻付きの銀杏を美味しく味わうにはいくつかの方法がありますが、最も手軽な選択肢の一つは電子レンジの活用です。しかし、電子レンジでは加熱の具合が難しく、加熱しすぎると実が爆発する恐れがあるほか、食感が硬くなりすぎてしまい、本来の美味しさを引き出しにくいという側面もあります。
より本格的に、そして風味豊かに銀杏を楽しみたいのであれば、フライパンでじっくりと炒る方法がおすすめです。この方法には、殻に少しヒビを入れてから殻ごと炒るやり方と、殻を完全に割って中の実だけを炒るやり方の二通りがあります。殻を剥いてから炒める方が、実の表面に香ばしい焼き色がつき、より風味豊かな仕上がりを堪能できるでしょう。
薄皮の剥き方と見た目の美しさ
銀杏の薄皮は食べても体に害はありませんので、剥かずにそのまま食べても美味しくいただけます。しかし、薄皮を剥くことで、銀杏本来の鮮やかな翡翠色が際立ち、料理の彩りとしてその美しさを存分に楽しむことができます。この美しい緑色は、見た目にも食欲をそそる効果があります。薄皮は、弱火で軽く炒るか、熱湯でさっと茹でることで、比較的きれいに剥くことが可能です。
銀杏の保存方法
収穫した銀杏を長期にわたって楽しむためには、適切な保存が重要です。殻が付いた状態のまま、密閉できる容器や袋に入れて冷蔵庫で保管すれば、数ヶ月間は品質を保つことができます。この保存方法を活用することで、旬の時期が過ぎてからも、美味しい銀杏を様々な料理に活用する楽しみが広がります。
全国に広がるギンナン栽培と主要品種
古くは食料難の際の貴重な保存食として重宝されてきたギンナンは、現在では日本各地で収穫されています。祖父江町におけるイチョウ栽培の歴史は深く、享保11年(1726年)に性海寺の僧によって、後に「久寿(くじゅ)」と呼ばれる品種の苗が植えられたことに始まると伝えられています。愛知県では、効率的な収穫のため、畑でイチョウの木を低く仕立てて栽培する独特の方法が採られています。また、佐賀県でも昭和30年代以降、タバコからの転作作物として積極的に栽培されるようになりました。
食用ギンナンのための栽培品種は多岐にわたり、晩生で大粒の「藤九郎(とうくろう)」、中生で大粒の「久寿(くじゅ)」(久治とも)、早生で大粒の「喜平」、早生で中粒の「金兵衛(きんべえ)」、中生で中粒の「栄神」などが代表的です。「藤九郎」は岐阜県(旧墨俣町)が発祥であり、「久寿(久治)」、「金兵衛」、「栄神(栄信)」、そして「長瀬」は愛知県稲沢市(旧祖父江町)で生まれた品種として知られています。
栄養価と独特の風味
ギンナンの実の中心部(仁)は、豊かな炭水化物を含み、そのもちもちとした独特の食感と、噛むほどに広がる歯ごたえが魅力です。さらに、タンパク質、脂質、カリウム、リン、鉄、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンCといった多様な栄養素も含まれています。独特のほろ苦さと芳醇な香りは、好みが分かれることもありますが、多くの人にとって秋の訪れを告げる特別な味覚として親しまれています。
まとめ
ジュラ紀から現代まで生き続ける「生きた化石」として知られるイチョウは、その特異な生態と息をのむような美しさで、私たちを魅了し続けています。学名「Ginkgo biloba」の語源、オスとメスが異なる木に育つ雌雄異株という神秘的な生殖様式、そして1895年に発見された遊泳精子の存在は、植物進化の重要な一端を物語っています。都市の街路樹としては最も多く植えられており、その強い生命力、耐火性、そして秋に見せる鮮やかな黄金色の葉は、都市景観の美化と防災の両面で計り知れない貢献をしています。
一方で、その種子であるギンナンは、秋の美味として珍重される一方で、**メトキシピリドキシン(MPN)による中毒のリスク**があります。特に小さなお子様は、少量でも中毒を起こす危険性があるため、摂取量には細心の注意が必要です。また、外皮にはウルシの成分と類似したギンゴール酸が含まれており、触れるとかぶれることがあります。イチョウ葉エキスは健康食品として利用されていますが、効果効能について科学的根拠が不足している場合もあるため、利用する際は成分規格や副作用、相互作用について確認しましょう。
日本の伝承、文学、さらには地名や家紋、髪型といった文化のあらゆる側面に深く根ざしているイチョウ。本記事が、イチョウが持つ多様な魅力と、その恩恵を安全に享受するための適切な知識を読者の皆様にお届けできることを心より願っています。