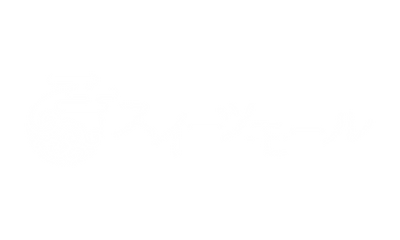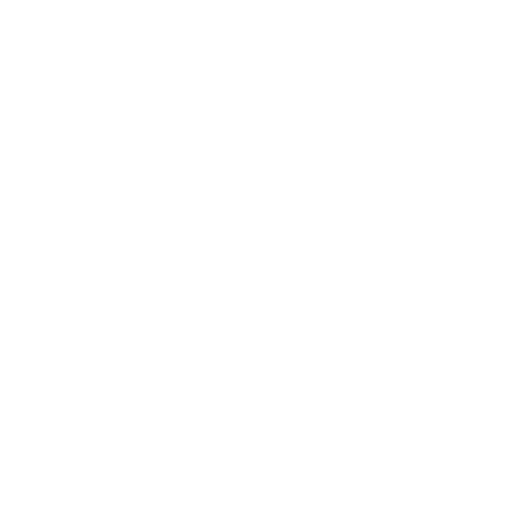千年の時を超え、古都京都で磨き上げられた京菓子。それは単なる甘味ではなく、日本の伝統文化を体現する芸術作品です。四季折々の繊細な美しさを閉じ込め、宮中文化や茶道との深い繋がりを持ち、職人の卓越した技と情熱が息づいています。この記事では、京菓子の定義、その悠久の歴史、比類なき芸術性、一般的な和菓子との違い、そして京都の年中行事や社寺との関わりを紐解きます。京菓子が持つ「目で楽しみ、耳で感じ、舌で味わう」という奥深い魅力を、具体的な菓子名や物語を交えながら、五感を通してご堪能ください。

京菓子とは?その定義と京都ならではの背景
京菓子とは、京都で長年の修行を積んだ職人が、京都の地で丹精込めて作り上げる和菓子のことです。その起源は、「都」である京都の菓子を、他の地域の菓子と区別するために生まれたという説があります。単なる甘味としてではなく、有職故実に基づいた儀式や典礼、伝統的な祭礼、芸術、そして茶の湯など、京都独自の文化の中で磨かれ、発展を遂げてきました。
特に、宮中や公家、社寺、そして茶家へ献上される「献上菓子」は、格別に「上菓子」と呼ばれ、庶民が日常的に食する菓子とは一線を画していました。これらの京菓子は、年中行事や四季の移ろいを大切にする京都の人々の繊細な美意識によって育まれてきたのです。日本の伝統菓子の総称である「和菓子」の中でも、京都という特別な場所で、独自の歴史と文化を背景に生まれたものだけが「京菓子」と称されるのです。その独自性と奥深さが、京菓子を特別な存在にしています。
京菓子の最大の魅力は、「目で味わい、耳で味わい、そして舌で味わう」という多角的な体験にあります。小さな菓子の中に、日本の四季折々の美しい風景が、見事な形と色彩で表現されており、視覚的にその美しさを堪能できます。さらに、京菓子には、和歌や古典文学、年中行事などに由来する趣深い「菓銘」が付けられていることが多く、その菓銘に込められた歴史や文化を知ることで、聴覚や想像力をも含めた五感で、その味わいはより一層深まります。そして、口にした時の繊細な舌触り、広がる芳醇な香りと味わいは、単に食べるという行為を超え、豊かな感動を与えてくれるのです。
京菓子の壮大な歴史と文化の融合
京菓子の歴史は、平安時代(794年~1185年)にまで遡ります。当時の日本の首都であった平安京(現在の京都)では、貴族文化が華開き、宮廷の儀式や行事で和菓子が用いられるようになりました。中国からの影響を受けながら、菓子作りは徐々に洗練されていきました。その後も、日本の歴史の変遷とともに、様々な外来文化や国内の文化が発展し、京菓子という唯一無二の菓子文化を形作っていったのです。
和菓子のルーツ:木の実・果物から始まった「菓子の始まり」
和菓子の起源は、古代の人々が飢えをしのぐために採取していた「木の実」や「果物」にあると言われています。食糧事情が十分でなかった時代、自然の恵みである果物の甘みは貴重なものであり、特別なものとして「果子」と呼ばれるようになりました。これが、和菓子の原点と考えられています。
古代からの甘味:田道間守と和菓子の起源
日本の和菓子の歴史を語る上で欠かせないのが、菓子の神様として知られる田道間守(たじまもり)の伝説です。彼は、垂仁天皇の命を受け、不老長寿の力を持つとされる「非時香菓(ときじくのかくのこのみ)」を求めて常世国(とこよのくに)へと旅立ちました。長い年月をかけて探し出したものの、帰国した時には天皇は既に崩御されており、田道間守はその霊果を墓前に捧げ、自らも命を絶ったと伝えられています。この非時香菓は、現在の橘(たちばな)、特に柑子蜜柑(こうじみかん)であると言われ、田道間守は菓子の神様として、京都の吉田神社内にある菓祖神社に祀られています。菓祖への敬意を込めて作られた菓子の一つに「夏柑糖(なつかんとう)」があります。夏蜜柑の果汁に寒天と砂糖を加え、再び夏蜜柑の皮に詰めて固めたもので、その爽やかな風味と上品な甘さが特徴です。
異文化との融合:唐菓子と南蛮菓子の足跡
京菓子の発展は、海外の文化の影響を大きく受けてきました。中でも、中国から伝わった「唐菓子」と、ポルトガルなどからもたらされた「南蛮菓子」は、日本の菓子作りに新たな技術と素材をもたらし、その進化を大きく後押ししました。
遣唐使が伝えた唐菓子:祭祀の供物から京菓子へ
7世紀から9世紀にかけて派遣された遣唐使は、仏教や様々な文化と共に、中国由来の菓子である「唐菓子(からくだもの)」を日本に持ち帰りました。平安時代の辞書『和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』には、梅枝(ばいし)、桃子(とうし)、餲餬(かっこ)、桂心(けいしん)、黏臍(てんせい)、饆饠(ひちら)、鎚子(ついし)、団喜(だんき)といった代表的な唐菓子の名が記されています。これらは主に小麦粉や米粉を使い、様々な形に成形して油で揚げたもので、当時は主に祭祀用として用いられ、日本の菓子文化に大きな影響を与えました。現在でも京都の一部の神社では、神前に供える菓子として、唐菓子の伝統を受け継いだ菓子が作られています。
この唐菓子の一つ「団喜」の製法を今に伝える京菓子が、「清浄歓喜団(せいじょうかんきだん)」です。京都の聖天さん(歓喜天)に供える特別な菓子として知られています。7種類の香辛料をブレンドした餡を、米粉と小麦粉を混ぜた生地で包み、蓮の花の形に象って胡麻油で揚げて作られます。その独特な香りと奥深い味わい、そして歴史的背景が、清浄歓喜団を特別な菓子として際立たせています。
ポルトガルが伝えた南蛮菓子:砂糖が生み出す新たな美味
戦国時代、ポルトガルやスペインの宣教師や商人によって、キリスト教と共に西洋の文化が日本にもたらされました。その中に「南蛮菓子」と称されるカステラ、ボーロ、カルメラ、金平糖(こんぺいとう)などがありました。これらの菓子は、卵や油、そして当時貴重だった砂糖を贅沢に使用しており、それまでの日本の菓子にはない濃厚な甘さと風味が人々を魅了しました。江戸時代の百科事典『和漢三才図会』に「加須底羅(かすていら)」や「阿留平糖(あるへいとう)」「糖花(こんぺいとう)」が紹介されていることからも、その影響の大きさが分かります。その後、南蛮菓子は日本の食文化に溶け込み、独自の変化を遂げながら、京菓子の一部として発展していきました。
特に「金平糖」は、その伝来に関する記録が残っています。1569年、織田信長が京都に上洛した際、宣教師ルイス・フロイスがキリスト教布教の許可を得るために献上した品の中に、フラスコ入りの「コンフェイト」がありました。これが日本の「金平糖」の始まりとされています。当時の人々は、その小さな粒が放つ輝きと色とりどりの色彩を、まるで宝石のように感じたことでしょう。金平糖は日本の菓子職人によって改良が重ねられ、現在では日本の伝統的な菓子として親しまれています。
茶の湯文化と京菓子の発展
鎌倉時代(1185年~1333年)には、武士による政権が力を増し、中国から禅宗が伝来しました。栄西が建仁寺を開き、道元が曹洞宗を、円爾が東福寺を開くなど、多くの僧侶が宋へ渡り禅を学びました。彼らは新しい仏教の教えとともに、禅僧ならではの生活様式を日本にもたらしました。その一つが、茶の湯と点心という食文化です。
禅僧と点心:饅頭の伝来と進化
饅頭は、禅僧が中国から持ち帰った食文化であり、本来は禅僧の軽食である「点心」でした。饅頭が日本に伝わった経緯には、主に二つの説があります。一つは、円爾が宋からの帰国後、博多の茶店主に製法を伝授したという説です。もう一つは、後に建仁寺の住職となる龍山徳見とともに、林浄因が来日し、初めて饅頭を作ったという説です。林浄因の子孫が店を構えた京都市内の「饅頭屋町」という地名は、今もその名残をとどめ、京菓子における饅頭の重要性を示しています。現代の饅頭は、つくね芋と砂糖、上用粉を混ぜた生地で、なめらかなこしあんを包み、蒸し上げたもので、和菓子を代表するものとして親しまれています。
茶道の隆盛と「京菓子」の確立
室町時代(1336年~1573年)になると、茶の湯はさらに発展し、茶室での茶会が盛んに開かれるようになりました。茶の湯の精神と繊細さが京菓子の発展に影響を与え、茶席で使われる和菓子としての地位を確立しました。千利休の茶会では「麩の焼き」がよく用いられ、「やきぐり」「せんべい」「焼き昆布」なども供されていました。1627年の茶会記に「京菓子」という言葉が初めて登場したことから、この時代に京都で独自の菓子文化が生まれたと考えられます。当時、茶の湯に集まったのは教養の高い権力者や文化人で、菓匠と協力し、季節感を表現した新しい菓子を創り出しました。
江戸時代(1603年~1868年)に入ると、平和な時代が訪れ、商業や芸術が発展しました。上流階級が食していた菓子が庶民にも広まり、茶の湯文化も浸透していきました。蒸し菓子や生菓子の「主菓子」、落雁や煎餅などの「干菓子」など、さまざまな京菓子が生まれました。1589年(天正17年)には、京都伏見の駿河屋岡本善右衛門が作った練羊羹が評判となり、江戸時代以降の京菓子は、宮中や社寺、大名への献上品として重宝されるようになりました。京都には茶道三千家(表千家、裏千家、武者小路千家)があり、その普及とともに、濃茶には生菓子、薄茶には干菓子が用いられるようになり、京菓子は美しい見た目と奥深い味わい、そして趣のある名前を持つ芸術的な菓子文化へと発展したのです。
王朝文学と年中行事の香り
京菓子は、平安時代の王朝文学にも登場し、当時の貴族の優雅な生活を伝えています。『源氏物語』や『宇津保物語』などの古典には、宮中で蹴鞠を楽しんだ貴族たちが、菓子や果物を味わう様子が描かれており、菓子が当時の貴族の生活に深く関わっていたことがうかがえます。
物語に描かれた雅な菓子文化
古典文学に登場する和菓子の例として、「椿餅(つばきもちい)」が挙げられます。古くは「つばいもちひ」と呼ばれ、もち米の粉に甘葛(あまずら)という甘味料を加え、椿の葉で挟んだものでした。この記述は、古の文化の優雅さを現代に伝える貴重な手がかりとなります。現在の椿餅は、道明寺粉を水で戻した生地で、なめらかなこし餡を包み、つややかな椿の葉で挟んで作られます。シナモンをまぶして風味を加えることもあり、その名前の響きも、鮮やかな葉の緑も、何とも言えない美しい菓子として、今も多くの人々を魅了しています。
江戸時代から現代へ:伝統を受け継ぎ、新たな息吹を吹き込む
江戸時代になると、長い戦乱の時代が終わり、平和な時代が訪れました。その結果、商業や芸術が大きく発展し、菓子職人たちは京都の伝統を守りながら、さらに創造的で洗練された京菓子を作り出すことに注力できるようになりました。京菓子の歴史は、およそ三百年以上にも及ぶとされ、その長い歴史の中で、和菓子職人たちの先人たちが厳しい修行を重ね、互いに腕を磨き合いながら、絢爛豪華な京菓子を創り上げてきました。
現代に至るまで、京菓子はその優美さや繊細さから、日本の伝統的な和菓子として広く親しまれています。茶道の文化とともに、京菓子は日本の歴史や風土を感じさせる独自の魅力を持っており、その伝統は今も大切に守られ、後世へと受け継がれています。しかし、京菓子は伝統を尊重する一方で、常に新たな感動を人々に提供することを追求し続けています。これまで培ってきた美を追求する伝統文化や技術を大切にしながらも、変化を恐れない京菓子の世界は、ますますその魅力の幅を広げています。
京菓子の本質:五感を満たす芸術
京菓子の芸術性は、その卓越した造形や色彩、そして四季の変化を繊細に表現した意匠によって、鑑賞者の五感を深く刺激します。それは単なる菓子という枠を超え、職人の感性と技術、そして日本の自然への深い敬意が凝縮された、小さな芸術作品と言えるでしょう。

造形と色彩:自然の美しさを映す匠の技
京菓子の造形は、職人の繊細な技術と豊かな感性によって創り出されます。とりわけ「生菓子」は、その形や色合いが非常に個性的で、まるで小さな芸術作品のようです。自然界から着想を得て、動植物や季節の情景など、多彩なモチーフが表現されます。色使いも細部にまでこだわり、自然の色を忠実に再現するために、時には天然の素材から色素を抽出して使用することもあります。その結果、菓子は奥深さと華やかさを兼ね備えた、美しい色彩をまとうのです。
生菓子に宿る、繊細な職人技
京の生菓子は、まるで小さなアート作品。季節の美しい情景を、見事に表現しています。例えば、「錦玉」。その名の通り、宝石のようにキラキラと輝く姿は、見た目にも涼やか。中には色とりどりの餡が透けて見え、その美しさに目を奪われます。春には、はらりと舞い散る「桜」の花びらを模したお菓子。夏には、清涼感あふれる「金魚」が水面を泳ぐ姿を表現したお菓子。秋には、色づき始めた「紅葉」や、夜空に浮かぶ「月」を象ったお菓子。冬には、きらめく「雪の結晶」をかたどったお菓子など、四季折々の風情を感じさせるお菓子が揃います。職人の熟練された技が光るこれらの生菓子は、私たちに季節の移ろいを鮮やかに伝えてくれます。
天然色素が彩る、奥ゆかしい美
自然の情景を映すため、古くは天然の染料が、現在でも厳選された色素が用いられ、繊細な色合いが表現されています。これらの自然な色合いが、お菓子に奥深さと上品さをもたらし、目で見て、舌で味わう、二重の楽しみを与えてくれます。職人の繊細な感性が際立つお菓子としては、「平安神宮の枝垂れ桜」をモチーフにしたものがあります。ピンク色の花びらが優雅に垂れ下がる様子が、見事な職人技で再現されています。繊細な金箔で表現された葉脈も美しく、まさに芸術品と呼ぶにふさわしい出来栄えです。京菓子の形と色は、日本の美しい自然と季節の移り変わりを繊細に表現しており、職人の技術と感性が凝縮されています。目で楽しみ、味わうことで、その奥深さを五感で感じることができるでしょう。
日本の四季を映すデザイン:情緒を味わう
京菓子の一つの特徴として、日本の豊かな四季や風物詩をモチーフにしたデザインが挙げられます。これは、日本人が昔から大切にしてきた季節感と深く結びつき、季節の移り変わりを愛でるという独自の文化を反映したものです。お菓子一つ一つが、その季節ならではの美しい情景を、私たちに語りかけてくれるかのようです。
春:息吹と桜の美
春のお菓子には、生命の息吹を感じさせる桜をモチーフにしたものが数多く登場します。代表的なのは「桜餅」。ほのかな桜の香りがする葉で包まれたお餅は、春の訪れを感じさせてくれます。また、桜の花びらの形をした「練り切り」は、桜の美しさと、散りゆく儚さを繊細に表現しています。その他にも、春の訪れを告げる黄色い「菜の花」をモチーフにしたお菓子は、新たな生命の誕生を祝うかのように、食卓を明るく彩ります。
夏:涼を呼ぶ水辺の風景
夏の京菓子は、見た目にも涼やかな意匠が凝らされています。例えば、水面を泳ぐ鯉を表現したお菓子や、青々と茂る草木を模ったお菓子など、目にするだけで涼を感じられるでしょう。特に、透明感あふれる「わらび餅」は、その見た目の清涼感に加え、つるりとした喉越しで、暑い夏に大変喜ばれるお菓子です。
秋:収穫の喜びと紅葉の彩り
秋の京菓子には、実りの秋を象徴する素材や、鮮やかな紅葉をイメージしたものが多く見られます。「もみじ饅頭」は、紅葉の形をしたお饅頭で、中には栗やさつまいもを使った餡が詰まっていることが一般的です。また、柿の葉で包んだ「柿の葉寿司」も、秋の収穫を祝う人々の気持ちを表していると言えるでしょう。店頭には、紅葉を模した練り切りや、栗、柿といった秋の味覚をふんだんに使用したお菓子が並びます。
冬:静寂と生命力、雪景色
冬の京菓子は、静かに降り積もる雪景色や、厳しい寒さの中で生き抜く生物の力強さを表現しています。「雪見だいふく」は、雪景色を眺めながら味わうことを想定して作られたお菓子で、その白さや柔らかな食感が雪を連想させます。また、「寒雀」をモチーフにしたお菓子は、冬の寒さの中で生きる鳥の姿を通して、力強さと美しさを伝えます。このように、京菓子は四季折々の情景を繊細に表現し、その季節ならではの趣を楽しむことができるのです。一つ一つのお菓子が、季節の移ろいとともに、様々な感情や風景を呼び起こします。
職人の卓越した技術と繊細な感性
京菓子は、熟練の技と豊かな感性を持つ職人が、丹精込めて一つ一つ手作りしています。その職人技こそが、京菓子の美しさと奥深い味わいを際立たせる、まさに真髄と言えるでしょう。長年の経験と磨き上げられた感性があってこそ、他に類を見ない唯一無二の京菓子が生まれるのです。
砂糖細工の粋:干菓子に息づく匠の技
京菓子の中でも、特に高度な技術が求められるのが「干菓子」です。砂糖と寒天を主な材料とするこの砂糖細工は、その繊細な形と鮮やかな色合いを表現するために、非常に優れた技術が欠かせません。干菓子には、小さな花や愛らしい鳥、日本の美しい風景などを精巧に表現したものがあり、これらは極めて細やかな手作業によって作り上げられます。特に色の美しさや形の繊細さは、職人の創造性が試される部分であり、一つとして同じものが存在しない、芸術性の高い作品として完成します。
餡と生地に秘められた伝統の風味と口当たり
京菓子において、餡はなくてはならない要素であり、その品質が菓子全体の味を大きく左右します。上質な餡を作るためには、豆の種類選びから、丁寧な炊き方、きめ細やかなすり方、そして入念な裏ごしといった細部にわたる技術が求められます。例えば、白餡は、そのなめらかな舌触りが特徴ですが、これは豆の皮を丁寧に除去し、最適な硬さに炊き上げることで初めて実現されます。また、生地作りにおいても、季節やその日の湿度に応じて材料の配合や練り具合を調整するなど、職人の長年の経験と繊細な感覚が味の決め手となります。さらに、京菓子は、その形や色を通して季節感を表現しますが、これもまた職人の感性が問われる点です。例えば、「練り切り」は、四季折々の美しい風景や風物を繊細に表現しますが、その色使いや造形の美しさは職人の洗練された感性によって生み出されます。また、「月見団子」は、中秋の名月を象徴するお菓子ですが、団子の形や盛り付け方によって、月の神秘的な美しさや趣を表現します。これらの菓子は、単に味わうだけでなく、その見た目や背景にある文化を感じることで、その真価を深く理解することができます。
京菓子の伝統を支える菓子型職人の手仕事
京菓子作り、とりわけ「押し菓子」の製造に必要不可欠なのが、木製の菓子型です。京都はもとより、日本各地で使用される菓子型の多くが、京都の職人の手によって製作されていると言われています。菓子型の材料には主に桜の木が使用され、3年もの歳月をかけてじっくりと乾燥させてから用いられます。古くから受け継がれる菓子の形に合わせて、細部に至るまで丁寧に彫刻された菓子型は、それ自体がひとつの工芸品としての価値を持ちます。この押し菓子用の木型の他に、打ち物に使用する金属型などもあり、伝統的な技術を現代に伝える菓子型職人の卓越した技術が、世界に誇る美しい京菓子の伝統を未来へと守り続けているのです。
茶道との優雅な調和:美意識と味覚の融合
京菓子は、日本の伝統文化である茶道と非常に深い関わりを持っています。茶席で供されるお菓子は、その見た目の美しさはもちろんのこと、一服のお茶の風味をより一層引き立てるという重要な役割を担っています。そのため、京菓子には、単に美しいだけでなく、お茶との調和を考え抜かれたデザインや味わいが求められます。京菓子は、茶道における「亭主のもてなしの心」を表現する上で欠かせない要素であり、お客様を心から歓迎し、季節感を共有するために、その時期に合わせたお菓子が選ばれるのが一般的です。
お茶席を豊かにする京菓子の役割
京菓子の中には、茶道のために特別に作られるものがあります。これらは、その季節ならではの趣を感じさせる形や色合いを持ち、茶室の雰囲気や茶会のテーマに合わせて選ばれることが多いです。茶道では、お菓子をいただいた後に口の中に広がる上品な甘さが、その後に味わう抹茶のほろ苦さをより一層引き立てると考えられています。そのため、京菓子は、味はもちろんのこと、食感や甘さのバランスが非常に重要視され、お菓子とお茶が互いを高め合う、絶妙な調和が生まれるように工夫されています。
おもてなしの心と季節感を伝える京菓子
茶道において、京菓子は単なる甘い食べ物ではなく、お客様をもてなす亭主の細やかな心遣いを表す大切な要素です。亭主は、お客様が心地よく過ごせるように、そして共に季節の移り変わりを深く感じられるように、その時期に最もふさわしい京菓子を選びます。たとえば、春には満開の桜をイメージした華やかなお菓子を、秋には澄み切った夜空に浮かぶ月をモチーフにした上品なお菓子を用意するといった具合です。これらのことから、京菓子は、その美しい見た目だけでなく、茶道の精神や美意識、日本の豊かな四季、そしておもてなしの心など、日本の伝統文化の様々な側面を体現していると言えるでしょう。
京菓子と和菓子の違い:定義と種類
京菓子と和菓子は混同されやすいですが、両者には明確な定義と分類の違いがあります。京菓子は、より広い意味を持つ和菓子の一種でありながら、京都という特別な歴史と文化の中で発展してきた、他に類を見ない存在です。
京菓子とは、京都で修行を積んだ職人が、京都の地で作る和菓子のことを指します。つまり、京菓子は和菓子の一種であり、日本の様々な和菓子の中でも、京都の職人が京都の地で、京都の文化や美意識を背景に作り上げたものだけが「京菓子」と呼ばれるのです。このような特別な名前で呼ばれるようになったのは、かつて「都」であった京都の菓子を、他の地域で作られる菓子と区別し、その格式と伝統を重んじるためでした。その伝統は現代まで受け継がれ、京都の和菓子は今も「京菓子」として愛されています。
一方、「和菓子」という言葉は、日本の伝統的な菓子の総称として用いられます。この言葉が使われるようになったのは、明治時代以降に海外から入ってきた「洋菓子」と区別するためという意味合いが強いです。一般的には、江戸時代までに日本に伝わり、独自の要素を取り入れて変化したお菓子を指すことが多いですが、その定義は明確ではありません。江戸時代以降に日本独自で生まれたお菓子を和菓子と呼ぶこともあります。共通する特徴としては、小豆や餅粉、米粉などを主な材料とし、上品で優しい甘さを持つことが挙げられますが、時代とともに味や見た目のバリエーションは増え続けています。日本が誇る食文化の一つとして、多くの人々に愛されているのが和菓子なのです。

京菓子の種類:生菓子、半生菓子、干菓子
京菓子は、水分量によって大きく「生菓子」「半生菓子」「干菓子」の3つに分けられます。それぞれの種類が持つ異なる魅力は、京都の四季折々の風景や、自然の美しさを愛でる京都の人々の美意識とともに育まれてきました。
生菓子:京菓子の代表、餡の芸術
京菓子を語る上で欠かせないのが生菓子です。主に餡を使い、その代表例として、餅菓子、蒸し菓子、饅頭、そして羊羹などが挙げられます。水分を30%以上含むため、しっとりとした食感が特徴で、多くは茶道、特に濃茶の席で、その深い味わいを引き立てる役割を担います。中でも、天正17年(1589年)に京都伏見の駿河屋によって創製された練羊羹は、生菓子の傑作として知られています。生菓子は、その繊細な意匠と上品な甘さ、そして四季折々の風情を表現したデザインで、京菓子の華やかさを象徴する存在と言えるでしょう。
半生菓子:生と干の間、味わいの妙
半生菓子は、生菓子と干菓子の中間に位置する菓子で、水分含有量は10%から30%です。生菓子より日持ちがするため、贈答品としても重宝されています。最中や求肥を使ったもの、あるいは餡を丁寧に形作ったものなど、様々な種類が存在します。生菓子の持つ瑞々しさと、干菓子の持つ趣深さを兼ね備えており、多様な場面でその美味しさを堪能できます。
干菓子:茶席を彩る、雅な存在
干菓子は、一般的に生菓子とは対照的な、乾燥した菓子の総称です。水分含有量が10%以下と低く、保存性に優れているのが特徴です。有平糖のように砂糖を凝縮させたもの、炒り種を使ったおこし、落雁や白雪糕のような打物、焼種で作られる煎餅や松風、軽焼など、その種類は多岐にわたります。茶道の薄茶席で供されることが多く、抹茶のほろ苦さを引き立てる、控えめながらも洗練された甘さが魅力です。
特に落雁は、打物干菓子の代表格と言えるでしょう。麦焦がしやきな粉などを主原料に、砂糖や水飴を加えて練り上げ、木型で成形し乾燥させて作られます。室町時代には、本願寺の綽如時芸が、もち米の粉を固め、黒胡麻を散らした菓子を、雪に舞い降りる雁に見立てて「落雁」と名付け、朝廷に献上したという故事があります。このように、干菓子一つをとっても、その背景には豊かな歴史と文化が息づいているのです。
京の四季を映す、京菓子の奥深さ
京都の和菓子店では、一年を通して楽しめる定番商品に加え、毎月、その季節や行事に合わせた特別な京菓子が店頭を飾ります。これは、京都の人々の生活に、古くから菓子が深く根ざしていることの証であり、季節の移ろいや年中行事を菓子を通して愛でる文化が、今もなお息づいていることを物語っています。

新春:新たな時を寿ぐ京菓子の宴
新たな年を迎える瞬間は、静謐でありながらも華麗な空気に満ち溢れます。新年の装飾や、新春を祝う茶会が開かれる家々では、心を新たにして味わう茶菓子にも格別な意味が込められます。
宮廷の伝統を受け継ぐ花びら餅
新春を祝う菓子として特に親しまれているのが「花びら餅」です。「菱葩」とも呼ばれ、明治初期に初めて製造したとされる老舗では「御菱葩」とも呼ばれています。この菓子は、薄く丸く伸ばした白い餅に、紅色の菱形の餅を重ね、甘く炊いた牛蒡と白味噌餡を包み込んだものです。今日では求肥を用いる京菓子店が多いですが、元々は宮中における正月行事で、貴族や官人に配られた菱葩が起源とされ、新年を祝う格式高い菓子として大切にされています。
年のはじめに願いを込める干支菓子と御題菓子
正月にはその他にも、その年の干支をモチーフにした「干支菓子」や、歌会始のテーマにちなんだ「御題菓子」が、京菓子の店頭を鮮やかに彩ります。これらの菓子には、その年の豊穣や安寧への願いが込められており、その美しい見た目とともに、菓子に託された意味合いを味わうことができます。
桃の節句:愛らしい娘の成長を願う雅な菓子
3月3日の桃の節句、ひな祭りには、女の子の無事な成長を祈る特別な菓子が欠かせません。雛人形の飾りとともに、色とりどりの菓子が飾られ、節句の趣をより一層引き立てます。
厄除けと成長を願う菱餅の彩り
ひな祭りの飾りとして親しまれるのが「菱餅」です。通常は、紅、白、緑の三色を重ねた餅ですが、地域によっては黄色や桃色を加えた五色のものも見られます。特に緑色の餅には、蓬が練り込まれており、古来より邪気を払う意味があるとされています。菱形が持つ形状は、春の息吹と力強い生命力を表し、女の子の健やかな成長を願う親心を映し出します。
宮中の儀式に由来する引千切
京都のひな祭りを彩る菓子として「引千切」も有名です。「ひっちぎり」や「ひちぎり」とも呼ばれ、外郎や、こなしで作られた土台に、色付けした白餡のそぼろを乗せた上品な菓子です。その起源は宮中で用いられた戴餅にあるとされ、伝統的な意味合いを持つひな祭りの菓子として、今も大切にされています。
春の訪れを告げる:桜を愛でる花見菓子
桜の開花とともに、人々の心をときめかせるのは、春の訪れを感じさせる美しい和菓子たちです。桜の下で、自然の美しさと共に味わう花見菓子は、日本の春ならではの楽しみです。
桜の情景を閉じ込めた花見団子と桜餅
花見の席に欠かせないのが「花見団子」です。緑、白、ピンクの三色の団子は、それぞれ新緑、雪、桜の花を象徴すると言われています。その色鮮やかな見た目は、満開の桜の下で味わうのにふさわしい華やかさです。そして、桜葉の香りが特徴的な「桜餅」もまた、春の定番です。道明寺粉で作られた生地で、滑らかなこし餡を包み、塩漬けの桜葉で丁寧にくるんでいます。特に、大島桜の若葉は香りが高く、桜餅の風味をより一層引き立てます。その他、桜をモチーフにした京菓子は数多く、そのどれもが京菓子ならではの繊細な意匠を凝らした上生菓子として、春の風情を豊かに表現しています。
お子様の成長を願って:端午の節句に味わう和菓子
五月五日の端午の節句は、男の子の健やかな成長と将来の成功を願う大切な日。この日には、家族の願いが込められた特別な和菓子が供えられます。
魔除けの粽と子孫繁栄を願う柏餅
端午の節句に欠かせない和菓子といえば、「粽(ちまき)」と「柏餅(かしわもち)」でしょう。平安時代に編纂された辞書『和名類聚抄』には、粽の製法とともに、五月五日に食す風習が記されています。米粉や葛粉を使い、円錐形に成形して笹の葉やイ草で包み蒸し上げた粽は、古来より邪気を払う力があると信じられてきました。一方、柏餅は、柏の葉が器の代わりに使用されていたことに由来すると言われています。柏の木は、秋に枯れ葉となっても春に新しい芽が出るまで葉が落ちないことから、「子孫繁栄」を象徴する縁起の良い木とされています。一般的には、米粉を使った生地でこし餡を包み、柏の葉で巻いて作られますが、地域によっては味噌餡や粒餡を用いるところもあります。
夏の厄払い:無病息災を祈る夏越の和菓子
六月三十日には、京都市内の多くの神社で「夏越(なごし)の神事」が執り行われます。境内に設置された茅の輪をくぐることで、半年間の心身に溜まった穢れを清め、無病息災を祈願する重要な行事です。この日に食すと厄除けになると伝えられる和菓子が「水無月(みなづき)」です。
氷をかたどった三角形:水無月
水無月は、米粉や小麦粉に砂糖を加えて水で溶き、型に流し込んで蒸し上げます。魔除けの効果があると言われる甘納豆の小豆を上に乗せて再び蒸し、三角形に切り分けるのが特徴です。生地には抹茶や黒糖を加えたものもあり、様々な風味が楽しめます。この三角形は、かつて京都の北山にあった氷室(ひむろ)から、夏に朝廷に献上された貴重な氷を模していると言われています。庶民は、簡単には手に入らなかった貴重な氷のかけらを模した和菓子を食することで、厳しい夏を乗り越えるための涼と、厄除けの願いを込めたのです。
京都の粋:祇園祭を彩る特別な和菓子
京都を代表する祇園祭は、日本三大祭りの一つとして広く知られています。その華麗な祭事とともに、祭りと和菓子の深い繋がりも見逃せません。祭りの期間中には、特別な意味を持つ様々な和菓子が登場し、祭りの雰囲気をより一層豊かなものにします。
稚児餅、行者餅、したたりに込められた祈り
長刀鉾に乗る稚児と禿が八坂神社に参拝した後、南楼門前の茶店で供されるのが、串に刺した餅に甘い白味噌を塗った「稚児餅」です。これは稚児たちの健やかな成長と、祭りの安全を祈願する和菓子です。また、役行者山に供えられ、宵山の一日のみ販売されるのが「行者餅」です。小麦粉と砂糖を混ぜた生地を薄く焼き上げ、粉山椒を混ぜ込んだ白味噌を塗り、餅を挟んで二つ折りにしたもので、役行者の篠懸を模した形とも言われ、無病息災への願いが込められています。さらに、菊水鉾に献上され、町会所に設けられた茶席で用いられるのが「したたり」です。寒天、黒砂糖、粗目、水飴を煮詰めて棹状に固めた琥珀羹で、透き通るような見た目が涼しげな和菓子です。菊水鉾は、名水として知られる菊水の井戸と、菊の露を飲んで長寿を得たという菊慈童の伝説に由来しており、この菓子もまた菊の露が滴る様子を表しています。
秋の風情:長寿と実りを願う重陽の菓子
9月9日は「重陽の節句」と呼ばれ、別名「菊の節句」としても親しまれています。奈良時代より宮中では菊を鑑賞する宴が催され、菊の花を愛でる文化が根付いていました。また、重陽の節句の前夜に菊の花に真綿を被せ、翌朝、露とともに菊の香りが移った真綿で顔を拭うと、若さを保ち長生きできると信じられていました。平安時代の貴族女性たちが、この風習を好んで行った様子が王朝文学にも描かれています。
観菊の宴と「着せ綿」の趣
現代ではあまり見られなくなった、古雅な行事を偲ばせる京菓子の「着せ綿」。こなし生地や、白餡に求肥を混ぜて作った練り切り生地で餡を包み、ヘラで丁寧に菊の形を作り、その上から白餡のそぼろを雪のように飾ります。これは、菊の香りを移した真綿を表現しており、長寿と健康を願う優雅な菓子として、秋の茶席を華やかに彩ります。
深まる秋から冬へ:伝統と祈りを込めた京菓子
古都、京都。今もなお、いにしえの宗教儀式が日々の暮らしに溶け込み、その多くは平安時代の宮中行事に起源を持ちます。秋が深まり、冬へと向かうこの季節、伝統的な京菓子は、人々の生活と祈りに静かに寄り添います。
無病息災と子孫繁栄を願う亥の子餅
晩秋の訪れを感じる11月、京菓子の店先には「亥の子餅(いのこもち)」が並びます。これは、求肥に黒胡麻やシナモン(肉桂)を練り込み、丁寧に炊き上げた粒あんを包み込んだもの。その形は、愛らしい猪(いのしし)の姿を模した俵型です。この菓子もまた、宮中行事であった「御玄猪(おげんちょ)」の儀式に由来し、多産な猪にあやかって、無病息災や子孫繁栄の願いが込められています。護王神社では、毎年11月1日に亥子祭が執り行われ、この由緒ある風習が大切に受け継がれています。
火焚祭を彩るお火焚饅頭と、季節を映す上生菓子
同じく11月には、各神社や町内のお稲荷さんで「火焚祭(ひたきまつり)」が斎行されます。これは、厄除けや無病息災を祈る神聖な祭典であり、そのお供え物として欠かせないのが「お火焚饅頭(おひたきまんじゅう)」と「お火焚おこし」です。祭りの後には、神様からの恵みとして、これらの菓子が氏子や町内の各家庭へと分け与えられます。京菓子の老舗では、燃え盛る火焔(かえん)を象った焼き印が印象的な饅頭が店頭に並び、祭りの賑わいを伝えます。火焚祭が終わる頃、京都は本格的な冬の装いへと変わり、菓子店には山茶花(さざんか)や寒椿(かんつばき)など、冬の草花を繊細に表現した美しい上生菓子が登場し、移りゆく季節の情景を鮮やかに描き出します。
社寺ゆかりの京菓子:歴史と信仰を今に伝える至高の品
京都の由緒ある神社仏閣では、古来より神饌(しんせん)や仏供(ぶく)として、常に菓子が供えられてきました。特に、格式高い紋章を木型で丹念に押し当てた落雁「御紋菓(ごもんか)」は、その代表格と言えるでしょう。神社の鳥居前や寺院の山門前は、神聖な場所への入り口として、多くの参拝者が行き交う場所でした。参拝者の増加に伴い、自然発生的に茶屋が設けられ、神仏の霊験あらたかな力に思いを馳せながら、お茶と菓子を楽しむという独自の文化が育まれました。これらの京菓子は、単なるお土産物という枠を超え、それぞれの社寺が大切に守り続けてきた歴史や、人々の篤い信仰心と深く結びついています。
寺院に由来する京菓子
京都の古刹には、その由緒や伝承に根ざした菓子が数多く存在し、今もなお参拝者に親しまれています。
方広寺:太閤秀吉が建立した大仏を偲ぶ大仏餅
方広寺は、太閤豊臣秀吉が建立を命じた京の大仏、盧舎那仏が鎮座していた寺院です。その門前に店を構える老舗が看板商品として販売したのが「大仏餅」の始まりと言われています。豊臣秀吉の時代の大仏餅と、現在販売されている大仏餅(甘春堂など)の間には、廃絶や復興の歴史がある場合があります。往時を偲んで復興され、現在も親しまれています。
西本願寺:戦の兵糧から生まれた「松風」
西本願寺と深い関わりを持つ菓子に「松風」があります。これはまさに西本願寺の歴史と運命を共にしてきたと言えるでしょう。織田信長による石山本願寺(現在の大阪城の場所)からの退去要求に対し、本願寺の顕如は徹底抗戦しました。この時、「松風」は兵糧として作られたと伝えられています。後に本願寺が京都に移転した後、顕如は「わすれては波の音かと聞くばかり 枕に近き庭の松風」と歌い、懐かしい兵食に「松風」という菓子の名前を与えました。小麦粉に味噌と砂糖を加えて焼き上げられた、裏面に焼き目のない独特の風味が持ち味の干菓子です。
大徳寺:一休禅師が広めた保存食「大徳寺納豆」
大徳寺と縁の深い「大徳寺納豆」は、蒸した大豆に塩水に浸した豆麹を加えて発酵させ、約2ヶ月間天日で乾燥させた濃褐色の塩辛納豆です。これは、室町時代の禅僧である一休禅師が中国の製法を伝授した禅僧のための保存食として知られています。大徳寺門前の一久は500年以上にわたってその秘伝の製法を伝えており、また1481年に一休禅師が亡くなった地である洛南・田辺町薪の一休寺(酬恩庵)でも、7月から9月にかけて同様の製法で「一休納豆」が作られています。独特の風味と塩味が特徴で、お茶請けや酒の肴として愛されています。
神社に伝わる伝統の味
古都京都の神社では、それぞれの歴史や故事にちなんだ和菓子が、参拝者をもてなしています。
下鴨神社:御手洗池の湧水から生まれたみたらし団子
下鴨神社といえば、やはり「みたらし団子」が有名です。串に刺して丁寧に焼き上げられた団子に、特製の甘辛いタレをかけたこのお菓子は、境内に鎮座する御手洗社の池から湧き出る水玉を模して作られたと伝えられています。一本の串に五つの団子が刺されており、一番上の団子が少し大きく、残りの四つの団子は間隔を空けて配置されていますが、これは人間の体を象徴しているという説もあります。かつては、神前で祈祷を受けた後、持ち帰って厄除けとして食されていました。
今宮神社:疫病退散の祈りを込めたあぶり餅
京都市北区紫野、今宮神社の東門前に佇む茶店で供されるのが「あぶり餅」です。小さく丸めた餅を細い竹串に刺し、炭火でじっくりと炙り、香ばしさを引き出した後、きな粉を混ぜた特製の白味噌をたっぷりとつけていただきます。その起源は平安時代、一条天皇が疫病の退散を祈願し、神前に餅を供えたことに遡るとされ、千年以上もの間、京の都で愛され続けている銘菓です。
北野天満宮:学問の神様と粟餅の深い繋がり
学問の神様、菅原道真公を祀る北野天満宮の門前にある粟餅を扱う店の看板商品が「粟餅」です。江戸時代に創業したという老舗で、もち粟を丁寧に蒸し、丹念についた餅は、上品な甘さの餡で包んだ「餡餅」と、香ばしいきな粉をまぶした「きな粉餅」の二種類が楽しめます。そのシンプルながらも奥深い味わいは、長きにわたり多くの参拝客に親しまれています。
上賀茂神社を訪れたら:神様へのお供え「やき餅」
シンプルに餅を焼き上げた「やき餅」は、京都では砂糖醤油につけたり、海苔で巻いたりして食されます。一方で、餅の中に甘さ控えめの小豆餡を詰め、両面を丁寧に焼き上げた「焼餅」は、古くから神社参拝のお土産として、門前で販売されてきました。現在も上賀茂神社の門前菓子として愛されており、素朴な味わいの中に、参拝の記憶が蘇ります。
地域と歴史が育んだ、多様な京菓子
京都には、特定の神社仏閣に限らず、その土地の歴史や文化の中で独自に発展してきた、バラエティ豊かな京菓子が存在します。
祇園:原了郭の伝統銘菓「祇園香煎」
祇園に店を構える「原了郭」は、「祇園香煎」で名高い香煎の老舗です。京都を代表する銘菓として広く知られています。元禄時代に創業し、赤穂浪士の一人、原惣右衛門の子である儀左衛門道喜が、漢方医からその製法を伝授され、商いを始めたとされています。紫蘇の香りが爽やかな紫蘇香煎や、香ばしいあられ香煎など、様々な種類の香煎を取り揃えています。
西陣:五節句の彩り「五色豆」
「五色豆」は、白、赤、茶、緑、黄の五色の砂糖をまとった豆菓子で、その色鮮やかな見た目から、お祝いの席などでも用いられる京名物です。明治17年頃、西陣の二軒の豆菓子店で作られたのが始まりとされ、その五色は宮中の五節句に由来する「王朝色」とも呼ばれています。見た目の美しさはもちろん、上品な甘さが特徴です。
亀屋清正が創製した「州浜」
「州浜(すはま)」は、炒った大豆を粉にしたものと、麦芽水飴を丹念に練り上げて作られる、シンプルながらも滋味深い京菓子です。その起源は古く、1595年(文禄4年)に亀屋清正(かめやせいしょう)によって考案されたと伝えられています。その後、1657年(明暦3年)には、丸太町通に店を構えていた植村義次(うえむらよしつぐ)が、蓬莱山を模した州浜台を創り、その意匠を凝らした州浜が評判を呼んだと言われています。江戸時代には、その上品な味わいから、朝鮮通信使をもてなす際にも用いられたという記録が残るほどです。今日では、13代目の当主が、伝統の製法を守りつつも、現代の嗜好に合わせた新たな州浜を次々と生み出し、その魅力を進化させています。
異国情緒あふれる「そばぼうろ」
「そばぼうろ」は、そば粉を主原料とした、異国情緒を感じさせる焼き菓子です。そのルーツは、かつて中京区蛸薬師姥柳町(なかぎょうくたこやくしうばやなぎちょう)に存在した南蛮寺などのキリスト教教会で、信者に供されていた小麦粉の焼き菓子「ボール」(オランダ語で「焼菓子」の意)にあると言われています。この製法に着想を得て、そば粉を用いて梅の形や小さな円形に焼き上げたものを、中京区に本店を構える総本家河道屋(そうほんけかわみちや)が「蕎麦ぼうろ」と命名し、世に広めました。サクサクとした軽やかな食感と、そばの芳醇な香りが特徴です。
奥ゆかしさを秘めた「味噌松風」
「味噌松風(みそまつかぜ)」は、小麦粉に上質な味噌と砂糖を加え、丁寧にこねて焼き上げた京菓子です。焼き上がった表面には、砂糖蜜を薄く塗り、けしの実やごまを散りばめて、風味と彩りを添えています。この菓子の特徴は、裏面に焦げ目がなく、その様子が「うら(裏)淋(さび)し」い情景を連想させることから、「松風」と名付けられたと言われています。紫野の味噌松風は歌人・烏丸光広(からすまるみつひろ、1579-1638年)が、また六条の松風は後水尾天皇(ごみずのおてんのう、在位1611-29年)がそれぞれ命名したという逸話も残っており、その歴史の深さを感じさせます。味噌独特の奥深い風味と、上品で優しい甘さが絶妙なバランスで調和しています。
筝曲家ゆかりの「八ツ橋」
「八ツ橋(やつはし)」は、上質なうるち米の粉に、砂糖とニッキ(シナモン)を加えて練り上げ、薄い短冊形に切り、独特の反りをつけて焼き上げた京菓子です。京を代表する銘菓として、全国的に広く知られています。その起源は、享保年間(1716-36年)に、箏曲八橋流(そうきょくやつはしりゅう)の祖である八橋検校(やつはしけんぎょう)の墓がある左京区黒谷(さきょうくくろだに)で、彼の愛用した琴の形を模した煎餅を販売したのが始まりであると伝えられています。その香ばしい風味と、他に類を見ない独特の食感は、京都を代表するお土産として、長い間多くの人々に愛され続けています。
まとめ
京菓子は、単なる甘さだけではなく、京都の千年を超える歴史と文化、そして職人の技が息づく、まさに芸術品です。その起源は平安時代の宮廷文化に遡り、唐菓子や南蛮菓子の影響を受けながら、茶の湯の発展とともに独自の進化を遂げてきました。四季折々の美しい自然を映し出す繊細な形と色合い、そして菓子の名に込められた物語は、五感を刺激し、単に味わう以上の豊かな体験をもたらします。和菓子の一種でありながら、「京都で生まれたもの」という明確なアイデンティティを持つ京菓子は、生菓子、半生菓子、干菓子など、その種類も豊富で、それぞれが京都の年中行事や社寺と深く関わっています。この記事を通じて、京菓子の歴史、芸術性、そして和菓子との違いをより深く理解し、古都京都が育んできたこの美しい伝統菓子の魅力を再発見していただけたら幸いです。京菓子を味わうことは、京都の精神と美意識に触れること。ぜひ、京都を訪れた際には、一つ一つの菓子に込められた物語を感じながら、五感でその美味しさを堪能してみてください。
京菓子と一般的な和菓子はどこが違うのですか?
京菓子は和菓子の一つの形ですが、特に「京都で技術を磨いた職人が、京都の地で作る和菓子」と定義されています。和菓子が日本の伝統的な菓子の総称であるのに対し、京菓子は京都特有の歴史、宮中文化、茶道、年中行事といった文化的背景の中で磨き上げられ、発展してきました。そのため、京菓子は単なる甘さだけでなく、その形、色、菓子の名前に深い意味や季節感が込められており、五感で楽しむことができる芸術性の高さが特徴です。
京菓子にはどのような歴史があるのですか?
京菓子の歴史は平安時代に始まり、宮廷文化や中国から伝わった唐菓子の影響を受けながら発展しました。鎌倉・室町時代には禅宗とともに饅頭などの点心が伝わり、茶道文化の発展とともに茶席を飾る生菓子や干菓子が工夫され、「京菓子」という言葉もこの頃から使われるようになりました。戦国時代には南蛮菓子が伝来し、江戸時代には庶民の間にも広まり、職人たちの手によって様々な京菓子が生み出されました。300年以上の歴史を持つ京菓子は、現在もその伝統と革新が受け継がれています。
京菓子はなぜそんなに美しいのですか?
京菓子の美しさは、職人の優れた技術と繊細な感性、そして日本の四季や自然に対する深い愛情から生まれます。生菓子は、動植物や季節の風物をモチーフにした精巧な形と、自然由来の色素を使った豊かな色彩で、まるで小さな芸術作品のようです。春の桜、夏の涼やかな水辺、秋の紅葉、冬の雪景色など、季節の移り変わりを繊細に表現したデザインは、日本人の美意識と共鳴し、食べる人に視覚的な感動を与えます。
京菓子はどんな時に味わうものですか?
京菓子は、普段のお茶請けやちょっとしたおやつとしてはもちろんのこと、季節ごとの行事、お祭り、お茶会といった特別な機会にも食されます。例えば、お正月には「花びら餅」、ひな祭りには「引千切」、端午の節句には「粽」や「柏餅」、祇園祭には「稚児餅」などが用いられます。また、茶道では、濃茶にはしっとりとした生菓子、薄茶には日持ちのする干菓子が選ばれ、お茶の風味をより豊かにする役割を担っています。それぞれのお菓子には、その背景にある文化や願いが込められており、口にすることで季節や行事の趣をより深く感じ取ることができるでしょう。
京菓子にはどのような種類があるのでしょう?
京菓子は、主に水分量によって「生菓子」「半生菓子」「干菓子」の3つに分類できます。 生菓子: 水分を多く含み、しっとりとした食感が特徴で、お餅を使ったもの、蒸し菓子、お饅頭、羊羹などがあり、茶道の濃茶席でよく用いられます。 半生菓子: 生菓子と干菓子の中間程度の水分量で、比較的日持ちが良く、最中や求肥を使ったお菓子などが代表的です。 干菓子: 水分量が少なく、日持ちするのが特徴で、落雁、お煎餅、松風、有平糖などがあり、茶道の薄茶席で用いられることが多いです。 これらの分類を基本として、季節や特別な行事に合わせた多種多様な京菓子が存在します。
茶道と京菓子はどのような関係なのでしょうか?
茶道と京菓子は非常に密接な関係にあります。京菓子は、抹茶の風味を一層引き立てるための「お供」としてだけでなく、お茶会において亭主のもてなしの心や、季節感を表現する大切な要素です。お菓子の形、色合い、そして菓子の名前が、その日のお茶会のテーマや季節の情景と調和するように選ばれます。お菓子を味わった後に口の中に広がる上品な甘さが、続く抹茶のほろ苦さを引き立てる効果も期待されています。京菓子は、茶道の美意識や精神性を表現する上で欠かせない存在と言えるでしょう。
京都で特に有名な京菓子は何ですか?
京都には、非常に多くの有名な京菓子が存在します。年中行事のお菓子としては、新春の「花びら餅」、夏の「水無月」、祇園祭の「稚児餅」や「したたり」などがよく知られています。特定の社寺に由来するものとしては、下鴨神社の「みたらし団子」、今宮神社の「あぶり餅」、西本願寺の「松風」、方広寺の「大仏餅」などがあります。その他、京都のお土産として広く親しまれている「八ツ橋」や「そばぼうろ」、「五色豆」、「州浜」、「味噌松風」なども、京都の歴史や文化と深く結びついた有名な京菓子です。