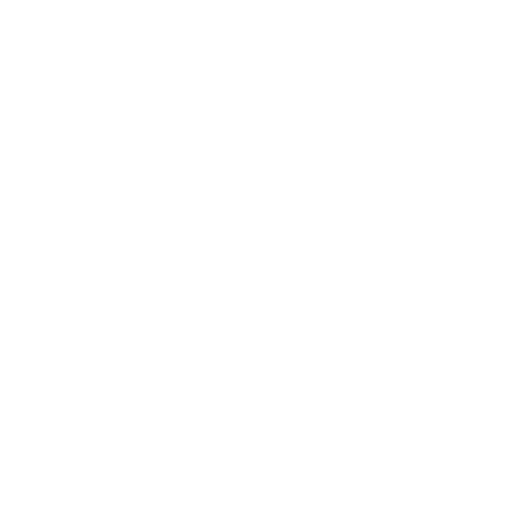世界には、お米のようにその土地の食文化を根底から支える「主食」が存在します。今回ご紹介するのは、世界三大穀物の一つであり、多様な食文化を支えるトウモロコシです。南北アメリカ大陸を原産とするトウモロコシは、今や世界中で栽培され、さまざまな形で食されています。甘くて美味しいだけでなく、栄養価も高く、人々の生活を支える重要な役割を担っているのです。この記事では、トウモロコシがどのように世界の食卓に根付き、多様な料理へと変化してきたのかを探ります。
トウモロコシ:多様性と世界を支える穀物
トウモロコシ(学名: Zea mays subsp. mays)は、イネ科の植物であり、その用途の広さと栽培面積の大きさから、世界で最も重要な穀物の一つとされています。食料としてだけでなく、家畜の飼料、バイオエタノール、コーンスターチ、コーン油といった工業原料としても利用されています。その生産量は非常に多く、2009年には年間8億1700万トンに達しました。米や小麦と並び、世界三大穀物として多くの地域で主食として食べられており、太陽の光が降り注ぐ畑で栽培されています。原産地はアメリカ大陸で、15世紀末にクリストファー・コロンブスによってヨーロッパに持ち込まれ、世界中に広まりました。日本へは16世紀末頃に伝わり、全国に普及しました。英語では一般的に「corn」と呼ばれますが、これは元々穀物全般を指す言葉でした。しかし、アメリカやカナダなどでは、特に指定がない限り「corn」はトウモロコシを意味します。ヨーロッパでは、主に「maize」(語源はスペイン語の「maíz」)と呼ばれています。日本では地域によって異なり、「トウキビ」、「ナンバ」、「モロコシ」など様々な呼び名があります。江戸時代の『本草図譜』(岩崎常正)にも紹介されており、日本においても古くから親しまれてきた植物です。
トウモロコシの呼び名に秘められた物語
日本語で一般的に使われる「トウモロコシ」という名前には、その伝来の歴史が反映されています。「トウ」は中国の王朝名である「唐」に由来し、「モロコシ」は唐から伝わったモロコシ(タカキビ)に似ていたことから名付けられました。日本に渡来した当時、最も似ている植物がタカキビだったため、その名が定着したと考えられています。地域によって様々な呼び名があり、北海道から北関東にかけては「とうきび」、西日本では「なんばんきび」と呼ばれることがあります。九州地方などで使われる「なんば」は、南蛮黍の略称であり、「高麗黍」と呼ぶ地域もあります。これらの呼び名は、トウモロコシが日本にとって外来植物であることを示唆しています。ヨーロッパでも同様に、フランスでは「トルコ小麦」、カナダのフランス語圏では「インド小麦」、イタリアでは「シチリア穀類」、スペインでは「インド穀類」など、「異国の穀物」という意味合いを持つ様々な名前で呼ばれていました。中国植物名は「玉米」です。これらの多様な呼び名は、トウモロコシが世界各地に広がり、それぞれの文化に根付いていった過程を物語っています。実際に、『日本方言大辞典』にはトウモロコシに関する267種類もの呼び方が掲載されており、地域ごとの生活と密接に結びついた名称の豊かさを示しています。
トウモロコシの知られざる植物学的特徴
トウモロコシは中南米原産の植物であり、高温で日照時間の長い環境下で特に良く育ちます。食用や飼料用として畑で広く栽培されており、長い年月をかけて様々な環境に適応した多くの品種が存在します。多くは一年生植物ですが、ごく稀に多年生のものも見られます。大型のイネ科植物であり、茎は一本で直立し、品種によっては高さ2メートル近くまで成長します。葉はイネ科としては幅広く、茎を抱き込むように下部が鞘状になって茎を包んでいます。一生のうちに付く葉の数や背丈は品種によってほぼ決まっており、一般的に早生品種ほど背丈が低く、葉の数も少ない傾向があります。熱帯生まれの植物であるため、光合成において二酸化炭素を効率的に濃縮するC4回路を持っているのが特徴です。そのため、日当たりが良く、やや高温の環境を好みます。大型の作物であるため、生育期間中を通して10アールあたり350〜500ミリリットルという大量の水を必要とします。
トウモロコシは雌花と雄花が同じ株に咲く雌雄同株の植物で、通常は風によって花粉が運ばれる他家受粉を行います。発芽から約3か月ほどで、雄花と雌花がそれぞれ別の場所にできます。雄花は茎の先端から葉よりも高く伸び出した花序に、雄花だけが密集した穂のような姿で現れます。一方、雌花は茎の下の方の葉の付け根あたりから出る円柱状の穂で、雌花全体が包葉に覆われており、上端から絹糸のような長い雌しべだけが、ひげ状に束になって外に伸び出しています。これがトウモロコシのひげと呼ばれる部分です。雄花から放出された花粉が、ひげ状の雌しべに付着すると、雌花の付け根が膨らみ、可食部である実(穀粒)が形成されます。完熟する頃には、ひげは茶色に変色して枯れます。イネ科植物としては珍しく、種子が熟すと穎(えい)の中から顔を出すのが特徴です。種子の色は黄色が一般的ですが、白、赤茶、紫、青、濃青など、非常に多様な色を持つ品種が存在します。トウモロコシの可食部となる実は、イネや小麦のように果皮に包まれた種子ではなく、子房全体が熟した果実そのものであるため、実の形質形成には受粉した花粉の力が強く影響する「異花受精効果」を受けやすいという特徴があります。
トウモロコシの起源と古代文明
メキシコでトルティーヤが広く親しまれている背景には、その主原料であるトウモロコシの原産地がアメリカ大陸にあるという事実に深く関係しています。スペインによる植民地化以前から、アメリカ大陸の先住民はトウモロコシを食生活の中心に据え、主食としていました。アメリカ大陸でのトウモロコシ栽培は、一説には紀元前3500年頃のメキシコやペルーで始まったとされますが、正確な年代特定は困難です。品種によっては、暑さ寒さに強い生命力を持つトウモロコシは、アメリカ大陸の多様な環境下、例えば高地や湿地を改良した畑などで栽培されてきました。そのため、先住民にとってトウモロコシは単なる食料ではなく、「神聖な植物」や「神からの贈り物」として崇拝されていました。しかし、初期のトウモロコシは、現代のものとは異なり、5センチに満たない小さな穂にわずかな実をつける程度だったと言われています。トウモロコシの起源に関しては、メキシコのハリスコ州からゲレロ州にかけて自生するテオシント(Zea mays mexicanaまたはEuchlaena mexicana)を起源とする説、絶滅した野生種とトリプサクム属(Tripsacum)の交配種とする説、またはトリプサクム属とテオシントの交配種とする説がありました。現在、最も有力なのはテオシント起源説であり、遺伝子解析の結果もそれを裏付けています。トリプサクム属起源説は否定され、テオシントとトウモロコシの分岐は約9200年前とされています。原産地は中米地域ですが、単一ではなく複数地域で別々に品種改良されたとする説が有力です。この小さな実から、現在の多様なトウモロコシ文化が育まれ、起源地からメキシコ高地で多様化した後、「メキシコ西部・北部 → 北米南西部 → 北米東部」または「メキシコ南部・東部 → グアテマラ → ユカタン半島 → 南アメリカ低地」へと伝播したと考えられています。南北アメリカ大陸では早くから主要穀物となり、ジャガイモやキヌアを除けば唯一の主穀として、マヤ文明やインカ文明を支えました。アンデス地域ではジャガイモなどの芋類が主食でしたが、トウモロコシも重要な作物であり、特に祭礼や儀式で用いられる酒(チチャ)の原料として大量消費されました。インカ帝国では階段状の農地を建設し、トウモロコシを大量に栽培していました。
旧世界への伝播と世界的拡大
新大陸で主要作物として発展したトウモロコシが旧世界へ伝播するきっかけは、クリストファー・コロンブスの新大陸発見でした。1492年、コロンブスがキューバ島でカリブ人が栽培していたトウモロコシをヨーロッパに持ち帰り、スペインに伝わりました。すぐに栽培が始まり、1500年にはスペイン南部のセビリアで栽培記録が残っています。経路は不明ですが、最初の大規模栽培はオスマン帝国で始まり、「トルコ小麦」と呼ばれました。珍しい植物であるトウモロコシは18世紀初頭まで課税対象外であり、従来の穀物から急速に転換していきました。16世紀半ばにはポルトガル沿岸に広がり、16世紀末にはフランスやイタリアにも広がり、ヨーロッパ全土に拡大しました。ヨーロッパでは当初、貧困層の食料として受け入れられましたが、従来の穀物よりも圧倒的に高い収穫率は、人口増加による圧力を緩和しました。大航海時代を迎えたヨーロッパ諸国の貿易船によって、トウモロコシは世界中に広がり、アフリカ大陸には16世紀に、中東にも16世紀初めに、そしてアジア東端の日本にも1579年に到達しました。1652年にオランダ東インド会社がアフリカ南端のケープ植民地に基地を建設した際、すでに現地のコイサン人にはトウモロコシが伝わっていました。アフリカでは伝播したものの、19世紀まではソルガムやミレットなどの在来作物の栽培が主流でした。しかし19世紀後半以降、鉱山労働者の食料としてトウモロコシの需要が増大し、労働者たちは帰郷後もトウモロコシを好むようになりました。さらに、トウモロコシはソルガムよりも早く成熟するため、端境期にも収穫できる点が普及を後押ししました。このため、特に南部アフリカや東アフリカでソルガムからトウモロコシへの転換が進みました。ただし、トウモロコシはソルガムよりも高温や乾燥に弱いため、サヘル地帯などの乾燥地帯では在来の雑穀を駆逐するには至りませんでした。一般的にはコロンブスがヨーロッパに持ち帰ったとされていますが、コロンブス以前に旧世界に存在し、12世紀のアフリカ、13世紀のシチリアで栽培されていたとする研究もあり、古代エジプト人が太平洋を越えてアメリカの産物をアフリカへ持ち込み、その中にトウモロコシが含まれていたという説も存在します。
日本への伝播経路と発展
日本へのトウモロコシ伝播には3つの経路があるとされ、最も古いのは南西経路と呼ばれるヨーロッパ人からの伝播です。平野長蔵は、1579年ごろ(安土桃山時代)にポルトガル人によって熱帯型の硬粒種(フリント種)が長崎にもたらされたとしています。日本ではキビに似ていることから「トウモロコシ」の他に「南蛮キビ」とも呼ばれ、漢名では黍、または玉蜀黍(玉は美しい、蜀は外国の意)と表記されました。その後、富士山麓や東北の山中、高知県など稲作に適さない地域に広がり、18世紀末には北海道のモロラン(現在の室蘭)に到達しました。当時は硬い硬粒種しかなかったため、救荒食として粥や餅に混ぜて使われることが多かったようです。江戸時代の農学者、宮崎安貞は『農業全書』(1697年)で菓子の原料に向くと記述し、人見必大の料理書『本朝食鑑』(1697年)には「火にあぶって食べるか、乾燥して粉にして餅にするのもよい」とあり、当時から多様な加工品として食されていたことがわかります。本格的な栽培は明治時代に入ってからです。明治初期には、近代育種法で作られたアメリカの早生デント種、フリント種が北海道に導入され、開拓使によって大規模な畑作が始まりました。トウモロコシは生食や飼料として定着し、東北地方や関東地方にも広がっていきました。この伝播経路は北海道経路と呼ばれ、南西経路とともに日本への主な伝播経路となりました。明治中期ごろからは、札幌狸小路(旧:札幌本願寺)の農家が始めた焼きトウモロコシ屋台が人気を博しました。1914年(大正3年)には「ゴールデンバンタム」が北海道で「黄金糯」として優良品種登録され、1929年(昭和4年)には日本食品製造合資会社の創始者が札幌市に缶詰工場を建設し、スイートコーンの缶詰製造を開始しました。1953年(昭和28年)にはアメリカから新しいスイート種が導入され、青果用の未熟トウモロコシ栽培が急増しました。育苗会社や農業試験場が世界中の苗を取り寄せて作り出した交雑品種が広く導入される事例が増え、この導入経路は自在経路と呼ばれています。1950年に開発された「ゴールデン・クロス・バンタム」が最初の例となり、1953年に日本に導入され、缶詰用・生食用として普及しました。さらに1971年(昭和46年)には坂田種苗(現:サカタのタネ)がスーパースイート種「ハニーバンタム」を導入し、従来よりも甘いトウモロコシが広まりました。
トウモロコシの栽培技術と管理
トウモロコシの栽培期間は一般的に4月中旬から8月で、春に種をまき、晩春から夏にかけて生長し、夏の7月から8月に収穫を迎えます。トウモロコシは高温と十分な日照を好み、栽培適温は22〜30度、発芽適温は25〜30度とされています。生育には高温が必要で、低温では発芽しにくいという特徴があります。正常な開花結実のための適温は12度以上35度以下です。霜にも耐えられますが、生育を促進するためには、雌花に多くの花粉が受粉できるように畝に2列以上で栽培することで受粉率を高めることが重要です。栽培土壌は弱酸性で有機質に富み、耕土が深く水はけの良い場所が適しています。トウモロコシの根は病害虫に強く、野菜畑の輪作作物として適していますが、一度切れると再生しないため、移植には向きません。養分吸収力が強く、一般的な肥沃な畑でよく育ちますが、食味の良い品種は生育が旺盛でないため、適切な追肥が必要です。トウモロコシは他家受粉性のため、受粉と受精が円滑に行えるように、同じ品種を1つの場所にまとめて栽培することが推奨されます。飼料用などの別品種が近くにあると交雑し、品種本来の特性が出せないため、同じ場所では1シーズンに1品種だけを作付けするか、別品種を植える場合は開花時期をずらすか、十分な距離を離して栽培するように管理します。種まきは4月中旬頃に行い、根が深く張るように元肥を多く施した畑を深くまで耕し、幅90cm以上の高畝を作ります。畝にはマルチングを行い、地温の保温と土壌乾燥を防ぎます。1か所あたり3〜4粒の種を、条間50cmの2列で30cm間隔でまき、2〜3cmの厚さに覆土します。十分に水やりをすると発芽するため、2回に分けて間引きを行い、草丈が10〜15cmくらいになるまでに最終的に1か所1本にします。間引きした苗は他の場所に植えて育てることもできます。苗を育てる場合は、育苗ポットなどに種をまき、発芽後の本葉が3〜4枚になったら定植します。トウモロコシは肥料の吸収力が強く、初夏の生長期には肥料を必要とするため、草丈30〜40cmくらいの時に追肥を行います。また、倒伏を防ぐために追肥と一緒に株元に軽く土寄せをします。雄花がついた時と雌花がついた時にも、それぞれ再度追肥を行うことが望ましいです。7月頃から1本の茎に雌花が数個つきますが、実を充実させるために芽かき(摘果)を行い、上から1つ、または2つだけ雌花を残します。摘果した雌花はベビーコーン(ヤングコーン)として食べられます。出穂以降の果実肥大期は水分が必要な時期なので、水切れを起こさないように管理します。雌花が受粉し、ひげが茶色に色づいた頃(受粉後20〜25日くらい)が収穫適期です。トウモロコシは鮮度が落ちやすいので、当日食べる分を早朝に収穫し、実が膨らんで充実していることを確認してから、根元から収穫します。トウモロコシの種や発芽直後の幼芽は鳥類の好物になりやすく、直播きの場合は食べられてしまうことがあります。鳥害から守るためには、育苗後に定植するか、直播きした上に不織布などを被せて防ぐ対策が有効です。発芽が揃い、緑色の葉が出たら、速やかに被覆材を取り外します。
メキシコ料理に欠かせないトルティーヤ:その製法と特徴
トルティーヤは、トウモロコシ粉から作られる薄焼きのパンであり、日本人が日常的に米を食するのと同じように、メキシコの人々にとってなくてはならない主食です。一般的なパンとは異なり、非常に薄いのが特徴で、例えるならピザ生地をさらに薄く伸ばしたようなものです。トルティーヤは、トウモロコシの粒をアルカリ性の石灰水で煮てから、石臼で挽いて生地(マサ)を作ります。そのマサを手で薄く円盤状に伸ばし、陶板(コマル)の上で焼き上げて作られます。メキシコ北部では、小麦粉で作られたトルティーヤも一般的です。石灰水を使用することで、トウモロコシの硬い皮が取り除きやすくなるだけでなく、ミネラルなどの栄養素も加わると言われています。現在でも、地方では伝統的な製法でトルティーヤが作られ続けています。
トルティーヤの豊富な食べ方:メキシコ伝統料理の例
メキシコでは、トルティーヤは様々な料理に使われます。例えば、トルティーヤに目玉焼きや炒り卵、唐辛子、トマトなどを添えた「ウェボス・ランチェロス」は、定番の朝食メニューです。「ウェボス」はスペイン語で「卵」を意味します。また、アボカドを使ったソースである「ワカモレ」につけて食べるのも一般的です。メキシコはアボカドの世界最大の生産国(2014年、国連食糧農業機関調べ)であり、ワカモレはメキシコ産の新鮮なアボカドに、トマトやライムなどを加えてペースト状にしたものです。トルティーヤの黄色とワカモレの緑色が食欲をそそります。さらに、トルティーヤを油で揚げてパリパリにした「トスターダス」、野菜や肉を挟んだ「タコス」、具材を挟んで半分に折り、ソースで煮込んだ「エンチラーダス」なども日常的に食べられています。日本でよく食べられているトウモロコシは甘みが強い品種が多いですが、メキシコでは甘みが少ない品種が主流です。また、黄色だけでなく、赤、黒、白など様々な色のトウモロコシが存在します。日本でもメキシコのように多様なトウモロコシが手に入るようになれば、食卓がより豊かになるでしょう。
品種改良がもたらすトウモロコシの多様性と国際的な影響
トウモロコシは長い栽培の歴史の中で、食用、飼料用、工業用など、様々な用途に合わせた品種改良が行われてきました。特に、消費者のニーズに応えるため、糖度や実の柔らかさ、食味などが重視され、世界中で多様な品種が開発されています。20世紀に入ると、「雑種強勢」という現象を利用したハイブリッド品種が開発され、トウモロコシの収量は飛躍的に増加しました。しかし、ハイブリッド品種は一代雑種であるため、農家は毎年種苗会社から種を購入する必要があり、アグリビジネスの巨大化を招きました。20世紀中頃には、ハイブリッド品種による収量増加の恩恵が発展途上国にも広がり、「緑の革命」を牽引しました。しかし、品種改良は主に飼料用トウモロコシが中心であり、主食用トウモロコシにおいては進展が遅れました。そのため、トウモロコシを主食とするメキシコやアフリカ諸国では、生産性が先進国ほど向上していない地域もあります。21世紀に入り、収量向上に加え、発展途上国で問題となっている栄養失調、特にビタミンA不足に対応するためのハイブリッド品種が開発され、ナイジェリアなどで試用されています。近年では、遺伝子組換え(GM)技術を用いた品種も普及しており、病虫害に強い品種が注目されています。トウモロコシの分類には、粒内の胚乳の構造によって種を区別する「粒質区分」が用いられます。粒質区分によって、品種の用途や栽培方法が異なり、主なものとしてデント種、ポップ種、フリント種などがあります。スイート種は未熟果として食用にされますが、その他は食品加工用や家畜の飼料として利用されます。「スイートコーン」は甘味種全般を指す総称です。
食用としてのトウモロコシ
トウモロコシは、主食、野菜、菓子、飲料の原料として、世界中で広く利用されています。乾燥したトウモロコシは穀物に分類されます。野菜として利用されるのはスイートコーンの未熟果で、旬は6月から9月ですが、鮮度劣化が早く、収穫後すぐに風味が損なわれるため、早めに調理する必要があります。生のトウモロコシは、焼いたり、茹でたり、蒸したりして食べるほか、サラダや和え物、炒め物、天ぷらなど、様々な料理に利用できます。加工品としては、コーンミール、マサ、コーングリッツ、コーンフラワーなどがあり、パンや菓子の原料として広く使われています。トウモロコシの栽培が始まったメソアメリカでは、トウモロコシは古くから重要な作物でした。乾燥させたトウモロコシの種子を石灰水で煮て処理(ニシュタマリゼーション)してからすり潰し、マサという生地にして、様々な料理に使いました。代表的なものが、メキシコで食べられているトルティーヤや、マサを具材とともに植物の葉で包んで蒸したタマルです。アンデス地域では、トウモロコシをアルカリ処理せずに粒のまま煮て食べることが多く、主食としてはジャガイモなどの芋類がより重要視されています。トウモロコシは煮て食べる以外に、発芽させたものを煮て糖化させ、発酵させてチチャという酒にすることも多いです。ヨーロッパやアジア、アフリカなどでは、トウモロコシを製粉して調理するようになり、アメリカ南部のハッシュパピー、イタリアのポレンタ、ルーマニアのママリガ、アフリカのウガリやパップ、中国のウォートウなど、様々な料理が生まれました。日本では、主食としての利用は一般的ではありませんが、かつては米の収穫量が少ない寒冷地や山間地で、トウモロコシを粥や餅にして食べる地域もありました。未熟な穂は、焼いたり茹でたりして野菜として食べられますが、スイートコーンが用いられることが多いです。野菜として特殊なものにベビーコーンがあります。ベビーコーンは、スイートコーンの2番目の雌穂を若採りしたもので、サラダや煮込み料理などに使われます。さらに特殊なものとして、メキシコではトウモロコシ黒穂病菌に感染した穂を「ウイトラコチェ」と呼び、食用とします。その他、コーンシチュー、バターコーン、コロッケ、ポップコーンなど、様々な料理に利用されています。南アフリカを中心とした南部アフリカでは、トウモロコシ粉を乾燥させたコーンミールを水や湯で溶かし、煮たパップというマッシュポテトのようなものが主食として食べられています。パップはトウモロコシの成分が濃縮されており、糖質を多く含むため、肥満の原因の一つともなっています。若干発酵させたものはサワーパップと呼ばれます。飲用としては、ビール、ウイスキー(主にバーボンやコーンウイスキー)、焼酎などの原料となる他、焙煎したトウモロコシを煮出したコーン茶もあります。ペルーで作られたチチャモラーダというアルコールを含まないジュースも存在します。
トウモロコシの栄養価と健康への貢献
トウモロコシは、主食としても用いられるほど豊富な炭水化物を持ち、野菜としてはエネルギー量が高い食品です。タンパク質や脂質に加え、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛といったミネラル類、そしてビタミンB1、B2、E、ナイアシンなどのビタミン群もバランス良く含有しています。トウモロコシの粒を覆う皮には、セルロースという不溶性食物繊維が豊富に含まれており、その量はジャガイモの約4倍。便秘の改善や大腸がんの予防に役立つとされています。また、トウモロコシ特有の黄色い色素はキサントフィルに由来し、血管の柔軟性を保つ効果が期待できます。白い部分に含まれるルテインは、コレステロール値を低下させ、動脈硬化の予防に寄与すると言われています。ただし、外皮は消化されにくい性質を持つため、胃腸が弱い方は過剰摂取を控えることが推奨されます。ビタミン類の中では、糖質のエネルギー変換を助けるビタミンB1が特に豊富です。文献によってはビタミンEが豊富と記載されている場合もありますが、特筆するほどの含有量ではありません。カリウムは野菜の中では比較的多く含まれています。一方で、トウモロコシの種子には、必須アミノ酸の一種であるトリプトファンが少ないという特徴があります。そのため、トウモロコシを主要な食料とする地域(南アメリカ、米国南部、ヨーロッパ山間部、アフリカの一部など)では、トリプトファン不足からくるナイアシン欠乏症、いわゆるペラグラ(皮膚炎、下痢、認知症を特徴とする病気)の発症リスクが高まる可能性があります。ただし、トウモロコシ原産地であるメソアメリカでは、古来よりアルカリ処理(ニシュタマリゼーション)を行うことでナイアシンの吸収を促進し、欠乏症を予防していました。
食用以外にも広がるトウモロコシの用途
トウモロコシは、人間が食料として消費するだけでなく、家畜の飼料としても大量に利用されています。2007年の統計では、世界のトウモロコシ消費量の64%が飼料用、32%がコーンスターチ製造やコーン油生産などの工業用として使用されました。特に、高純度のデンプンを効率的に抽出できるため、工業原料としての重要性が高く、胚乳から得られるデンプンは、紙や繊維製品の製造に利用されるほか、発酵させてエタノールや乳酸といった様々な化学物質に変換されます。こうして生成される異性化糖は、甘味料として広く使用されています。近年、バイオマスエタノールやバイオプラスチックなどのバイオ燃料、バイオ素材への関心が高まっており、特に米国では自動車燃料としての利用が拡大しています。また、飼料用トウモロコシの実を燃料とする暖房用ペレットストーブ(通称「コーンバーナー」)も製造・販売されています。米国では、バイオマスエタノールの原料としてのトウモロコシ需要が急増し、2008年には国内需要の3割を占めるまでに至りました。この需要増に対応するため、大豆や小麦からの転作が進んでいますが、トウモロコシは他の作物に比べて成長に大量の水を必要とするため、一部地域では水資源の不足が懸念されています。さらに、エタノール相場とトウモロコシ相場の不均衡、輸送インフラの未整備による採算性の悪化、エタノール対応車の普及の遅れなどから、バイオマスエタノールの需要は伸び悩んでいます。その結果、エタノール価格はガソリン価格の高騰にもかかわらず低迷するなど、課題も抱えています。その他、トウモロコシの実や発芽直後の幼芽は、鳥釣りの餌としても利用されます。また、漢方では玉蜀黍(ぎょくしょくしょ)と呼ばれ、胃腸の調子を整える生薬として用いられ、茹でて食用にされます。トウモロコシの種子から抽出される脂肪油は、薬の溶剤や軟膏の基剤として使われます。文化的な側面では、「インディアンコーン」と呼ばれる品種が、北米の先住民の間で感謝祭などの収穫期に、ドアやテーブルを飾る習慣があります。
軸(コーンコブ)
実を取り除いた後の軸(コーンコブ)は、燃料や活性炭、研磨材などの製造原料として活用されます。粉砕されたコーンコブミールは、キノコの培地、家畜の飼料原料、有機廃棄物の吸収材などとして利用されます。芯が柔らかく、円筒形に加工しやすいことから、喫煙具(コーンパイプ)の材料としても用いられます。第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官を務めたダグラス・マッカーサーがコーンパイプを愛用していたことはよく知られています。現在流通しているコーンパイプは、1946年に芯の利用を目的に開発された専用品種を材料として製造されています。
茎・葉
トウモロコシの茎や葉は、家畜の飼料やすき込み用の緑肥として利用されます。青刈りトウモロコシは、これらの目的のために栽培されます。収穫後に放置し、乾燥したものを裁断して土に混ぜ込むことで、肥料として利用することも可能です。種子が硬く、色彩が美しい品種は、包葉を取り除くか、バナナの皮のように剥いて乾燥させ、観賞用として楽しむことができます。取り除いた包葉は、繊維や布の代用品として利用されることもあります(包葉を使ったバスケットなど)。北海道では、1947年頃からトウモロコシの皮(きみがら)を材料にした「きみがら細工」が編まれ、特産品となっています。
花柱
雌しべから伸びる花柱、いわゆるトウモロコシのヒゲは、成熟して褐色に変わり乾燥したものを採取し、日光で十分に乾かします。これは生薬として「玉蜀黍蕊(トウモロコシズイ)」、または「玉米鬚(ギョクベイシュ)」と呼ばれ、日本国内では「南蛮毛(ナンバンモウ)」の名で知られています。南蛮毛には利尿作用があり、体内の余分な水分を排出する効果が期待できます。この利尿作用は、南蛮毛に豊富に含まれるカリウムによるもので、カリウムが塩分と結合して体外へ排出を促すことで、むくみの軽減や血圧の安定に貢献すると考えられています。副作用が少ないため、コーン茶として日常的に飲用することも可能です。南蛮毛は、初期の『日本薬局方』に収載されていた「バクモンドウ」という利尿薬の代替品として用いられるようになりました。中国医学においては、利尿作用のほか、急性腎炎、妊娠時のむくみ、糖尿病、高血圧、慢性腎炎などの症状に対し、乾燥したヒゲ状の部分を5〜10g、300〜600mlの水で煎じ、1日に3回に分けて服用する方法が知られています。現代中国の研究では、血糖値を下げる作用、胆汁の分泌を促進する作用、止血作用などが確認されており、これらの効果に着目して、高血圧、糖尿病、腎炎、膀胱炎などの治療薬として利用されています。
遺伝子組換え(GM)コーンの現状
遺伝子組換え技術を用いて開発されたトウモロコシ、通称「GMコーン」は、世界の農業生産において重要な位置を占めています。GMコーンの穀粒そのもの(袋詰め、サイロ貯蔵、はしけ輸送など)や、それを粉砕して作られるコーングリッツ、コーンパウダー、コーンフラワー、コーンミールなどの加工品については、遺伝子組換えの有無を検査するため、トウモロコシ固有の遺伝子であるSSIIb(スターチシンターゼ IIb)を指標として、リアルタイムPCR法などの分子生物学的な手法を用いた定量検査が行われます。これにより、食品や飼料としての安全性が確認されています。意図しないGM作物の混入を考慮し、日本では大豆とトウモロコシにおいて、5%以下の混入であれば取引が許可されています。これは、非遺伝子組換え製品であっても、微量のGM作物が混入する可能性を考慮した措置です。日本におけるGMコーンの流通と利用は、厳格な審査と管理体制のもとで行われており、検査方法については、JAS分析試験ハンドブック『遺伝子組換え食品検査・分析法』(第3版、平成24年9月24日)や『安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法』の別添に、検査方法と対象となる系統が詳細に記載されています。厚生労働省は、食品または飼料としての利用、栽培、加工、保管、運搬、廃棄などに関するGMコーンの承認を継続的に行っており、バイオセーフティークリアリングハウス(J-BCH)のウェブサイトに登録されているGMコーンは、2019年8月時点で112件に達しています。これには、後代系統や使用期限切れの系統も含まれており、これらの情報は市場の透明性を確保する上で重要な役割を果たしています。近年、病害虫への抵抗性を高めるために遺伝子組換えを行った品種が世界的に普及しています。輸入された遺伝子組換えトウモロコシは、スーパーなどで販売されている一般的な食品に含まれる植物性油脂、ブドウ糖、水あめ、異性化糖、デンプン、アルコールなどの原料として、日本国内で広く利用されています(日本では、トウモロコシを含む8種類の農産物と、それらを原材料とする33種類の加工食品のみが表示義務の対象であり、上記のような加工品には表示義務はありません)。現在のところ、日本では遺伝子組み換え作物の商業栽培は行われていません。
世界の生産量と主要生産国
日本で一般的に消費されているトウモロコシは、スイートコーンと呼ばれる甘味種が主流ですが、世界全体で見ると、飼料や工業原料として利用されるデントコーン(馬歯種)の栽培が圧倒的に多くを占めています。飼料、デンプン、油の原料となるのは、デントコーンやワキシーコーンなどの品種であり、そのほとんどを輸入に頼っています。日本国内の主な産地は、千葉県、北海道、群馬県、茨城県、山梨県、愛知県などですが、生鮮または冷凍トウモロコシの主な輸入先は、アメリカ、オーストラリア、中国、ニュージーランド、台湾などです。乾燥または粉状のトウモロコシは、アメリカ、ベトナム、台湾、中国、タイなどから輸入されています。2017年の世界のトウモロコシ総生産量は約11億6440万トンに達し、そのうちアメリカが3億9760万トン以上を生産し、世界全体の3割強を占める最大の生産国です。2010年から2019年までの10年間では、アメリカ合衆国、中国、ブラジル、アルゼンチン、インドが生産量の上位5カ国となっています。
国際貿易と市場動向
2010年から2019年までの10年間の国際取引においては、輸出国のトップ5は、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ブラジル、ウクライナ、フランスであり、輸入国のトップ5は、日本、メキシコ、韓国、エジプト、EU(欧州連合)です。中国は世界第2位の生産国ですが、国内需要を満たすことができず、近年輸入量が増加傾向にあり、2019年には497万トンの輸入を行っています。アメリカは世界最大の輸出国であり、そのシェアは約3割を占めています。そのため、アメリカの主要生産地域の天候状況が、世界の在庫量や価格に大きな影響を与え、国際的な投機商品の対象となっています。トウモロコシは国際的な穀物取引の主要な商品であり、シカゴ商品取引所(CBOT)で先物価格が決定されるほか、東京商品取引所(TOCOM)でも取引されています。
日本におけるトウモロコシの流通実態と消費構造
日本はトウモロコシの大部分を輸入に頼っており、食糧管理に関する統計や、農業・食品産業技術総合研究機構などが示す統計区分では、トウモロコシは穀物に分類されています。その輸入量は年間およそ1600万トンにも達し、これは日本の年間米生産量の約2倍に相当します。日本は世界で最もトウモロコシを輸入している国の一つです。輸入量の約9割はアメリカからのもので、国内で消費されるトウモロコシの75%は、家畜の飼料として使用されています。飼料用としては、「青刈りトウモロコシ(サイレージコーン)」と呼ばれる粗飼料や、「子実を利用するトウモロコシ」と呼ばれる濃厚飼料が、国内の酪農家などで生産されており、年間450万トンから500万トン程度の収穫があります。しかし、そのほとんどが自家消費されるため市場には出回らず、統計上、これらの飼料用トウモロコシの自給率は0.0%と見なされています。
一方で、まだ熟していない状態で収穫され、一般的に小売店や飲食店で販売される甘味種は、統計上「スイートコーン」と呼ばれ、野菜として扱われます。日本の年間国内生産量は25万トンから30万トン程度ですが、生のスイートコーンの輸入量は10トン程度と非常に少なく、店頭で販売されている生食用スイートコーンは、ほぼ全てが国内産です。ただし、冷凍や加工されたスイートコーンの輸入は、年間9万トンから10万トンほどあります。平成22年度のスイートコーン国内総生産量は23万4700トンで、都道府県別に見ると、最も生産量が多かったのは北海道(道内各地、特に十勝、上川地方)で10万7000トンに達し、国内総生産量の約40%を占めています。次いで生産量が多いのは、千葉県の1万6900トン、茨城県の1万4500トン、群馬県の1万0400トン、山梨県の9400トンとなっています。国内で生産されるスイートコーンは、缶詰の原料や、そのまま食用として利用されます。
トウモロコシの多様な消費形態と経済的影響
2007年のトウモロコシの世界消費量を見ると、家畜の飼料用が64%と最も多く、コーンスターチ製造などに使用される工業用が32%を占め、直接食用はわずか4%に過ぎません。トウモロコシの直接食用としての消費量は、国によって大きく異なり、アメリカや中国のように生産量が多い国でも、あまり食用には用いないという特徴があります。最も食用としての消費が多いのは、トウモロコシから作られるトルティーヤを日常的に食べるメキシコや、パップ、サザ、ウガリといったトウモロコシ粉から作られる食品を主食とする、アフリカ東部から南部にかけての地域です。なお、主食用トウモロコシと飼料用・工業用トウモロコシは品種が異なるため、飼料用トウモロコシの消費を減らして主食用に転換することは、単純にはできません(主食用を飼料用や工業用に転用することは可能です)。かつて2008年にケニアで大飢饉が発生した際、アメリカ合衆国がトウモロコシ粉を食料として援助しましたが、その粉がケニアでウガリなどに使用する白いトウモロコシではなく、ケニアでは食用としない黄色いトウモロコシであったため、ケニア政府が援助をアメリカに返却したという事例もありました。近年、最大の生産国であるアメリカにおいて、トウモロコシを原料とするバイオエタノールの需要が急速に増加し、エタノール用のトウモロコシ需要は1998年の1300万トンから2007年には8100万トンまで急増しました。これによりトウモロコシの需要は拡大しましたが、一方で生産が需要に追いつかず、従来の食用・飼料用の需要と競合する形となり、価格が急騰し、世界的な食糧危機を引き起こした原因の一つになったという見方もあります。
まとめ
この記事では、メキシコの食文化に欠かせないトルティーヤに焦点を当て、その原料であるトウモロコシの奥深い世界を探求しました。トウモロコシは、約9200年前にテオシントという植物から派生し、アメリカ大陸を原産として紀元前3500年頃から栽培されてきた長い歴史を持ち、古くからマヤ文明やインカ文明の基盤を支え、「聖なる植物」として崇められてきました。15世紀末には、クリストファー・コロンブスによってヨーロッパに伝えられ、その高い収穫率から世界各地に急速に広まり、貧困層の食料源として、また大航海時代を経てアジアやアフリカにも伝わりました。日本へは1579年ごろに南西ルートで伝わり、明治時代には北海道開拓とともに栽培が本格化するなど、様々な経路を経て普及しました。その学術的な特徴から、世界中で多様な名称を持つことになった経緯、そして4月中旬から8月にかけて行われる具体的な栽培方法、肥料の管理、鳥による被害対策まで、その生態と農業技術について詳しく解説しました。メキシコでは、トウモロコシを石灰水で処理し、臼で挽いた生地「マサ」から作られるトルティーヤが日常的に食され、「ウェボス・ランチェロス」や「タコス」、「エンチラーダス」など、多様な料理に形を変えます。日本のスイートコーンとは異なり、甘味が少なく様々な色の品種が主流であるメキシコのトウモロコシ文化は、私たちの食卓にも新たな発見と豊かな食体験をもたらす可能性を秘めています。また、世界的な生産量と流通の実態、特にアメリカが最大の生産・輸出国であること、雑種強勢を利用したハイブリッド品種の開発がアグリビジネスの巨大化を促進し、発展途上国での緑の革命をもたらした一方で、飼料用トウモロコシの開発に偏った影響や、栄養失調対策としての品種改良の試み、さらには遺伝子組換えトウモロコシの現状と日本国内での流通、そして食用・飼料用・工業用としての利用、バイオエタノール需要が食料価格に影響を与える国際的な側面についても考察しました。トウモロコシは食用としてだけでなく、栄養価が高く、軸、茎、葉、花柱に至るまで、多岐にわたる用途があることがわかりました。この記事を通して、世界の主食とその背景にある文化や歴史、そして現代における経済的な影響について理解を深めていただければ幸いです。
トルティーヤとは何ですか?
トルティーヤは、主にトウモロコシの粉で作られる薄いパンであり、メキシコではお米のように日常的に食べられる主食です。普段私たちが食べる食パンとは異なり、ピザ生地をさらに薄く伸ばしたような形状をしているのが特徴です。
トルティーヤはどのように作られますか?
伝統的な製法では、乾燥トウモロコシをアルカリ性の水溶液(石灰水)で煮て、皮を取り除いた後、石臼などで丁寧にすり潰して生地(マサ)を作ります。この生地を手で薄く円形に成形し、熱した鉄板や平鍋(コマル)で焼き上げます。石灰水で煮ることで、トウモロコシの表皮が柔らかくなり、同時に栄養価も向上すると考えられています。メキシコ北部地域では、小麦粉を原料としたトルティーヤも一般的に食されています。
メキシコでトウモロコシが主食となったのはなぜですか?
メキシコにおいてトウモロコシが主要な食料となった背景には、この地域がトウモロコシの発祥地であることが大きく影響しています。紀元前3500年頃からメキシコを含むアメリカ大陸で栽培が始まり、先住民文化の中で「神聖な植物」として崇拝され、生活の中心的な役割を担ってきました。マヤ文明やインカ文明などの古代文明では、トウモロコシの大規模な栽培が行われ、社会の発展を支える基盤となっていました。
トウモロコシはどのように世界に広まりましたか?
15世紀末、クリストファー・コロンブスがアメリカ大陸からヨーロッパへトウモロコシを持ち帰ったことが、世界への普及のきっかけとなりました。栽培の容易さと高い収穫量から、ヨーロッパ各地で急速に広まり、その後、大航海時代を通じてアフリカ、アジア、そして日本を含む世界各地へと伝播していきました。日本へは16世紀後半にポルトガル人によって伝えられ、明治時代にはアメリカから新たな品種が導入されました。現代では甘味種(スイートコーン)が広く栽培されるなど、複数のルートを経て普及が進んでいます。
トウモロコシの栽培で気をつけるべき点は何ですか?
トウモロコシは、日当たりが良く温暖な気候を好みます。栽培に適した気温は22〜30℃、発芽には25〜30℃が必要です。安定した収穫のためには、複数の列で栽培し、雄花と雌花が確実に受粉するように工夫することが重要です。また、肥料を多く必要とするため、生育段階に応じて追肥を行うことが大切です。草丈が30~40cmの頃と、雄花・雌花が出始めた頃に肥料を与えましょう。鳥による被害を防ぐためには、苗を植え付けた後に不織布などで覆うことが効果的です。収穫時期は受粉後20〜25日程度が目安で、鮮度が落ちやすいため、収穫は早朝に行い、できるだけ早く食べるのがおすすめです。
メキシコのトウモロコシは日本のものとどう違いますか?
日本で一般的なトウモロコシは、強い甘みが特徴のスイートコーンが主流ですが、メキシコでは甘みが控えめな品種が多く栽培されています。さらに、メキシコ原産のトウモロコシは、黄色だけでなく、赤、黒、白など色彩豊かで、品種も多種多様です。これらのトウモロコシは、日本の食文化に新たな彩りをもたらす可能性を秘めていると言えるでしょう。また、メキシコでは、トウモロコシを石灰水で処理するニシュタマリゼーションという伝統的な調理法があり、これによってトウモロコシの栄養価が高まり、体への吸収率が向上します。
トウモロコシにはどのような食用以外の用途がありますか?
トウモロコシは、食料としてだけでなく、様々な分野で活用されています。世界全体の消費量の約64%は家畜の飼料として利用されており、その他、コーンスターチやコーン油といった工業製品の原料としても重要です。近年では、バイオエタノールの原料としても注目を集めています。また、実を収穫した後の芯(コーンコブ)は、燃料や活性炭、コーンパイプの材料として再利用されます。茎や葉は、家畜の飼料や緑肥として活用されます。さらに、トウモロコシの雌しべである「ひげ」は、南蛮毛と呼ばれ、利尿作用のある生薬として用いられ、むくみの解消や高血圧の改善に役立つとされています。
日本におけるトウモロコシの主な流通実態はどうなっていますか?
日本は世界有数のトウモロコシ輸入国であり、年間約1600万トンものトウモロコシを輸入しています。その中でも、約9割をアメリカからの輸入に頼っています。輸入されたトウモロコシの約75%は、主に家畜の飼料として消費され、デントコーンやワキシーコーンといった品種が中心です。国内でも飼料用トウモロコシ(サイレージコーンなど)は年間450万~500万トン生産されていますが、そのほとんどが自家消費されるため、統計上の自給率は非常に低いのが現状です。一方、生食用として人気のスイートコーンは、国内生産が年間25万~30万トン程度で、店頭に並ぶものはほぼ国産です。しかし、冷凍や加工用のスイートコーンは、年間9万~10万トンが輸入されています。輸入された遺伝子組換えトウモロコシは、植物性油脂、ブドウ糖、水あめ、デンプン、アルコールなどの加工食品の原料として広く利用されていますが、これらの加工食品には遺伝子組換え表示の義務がないという点に注意が必要です。