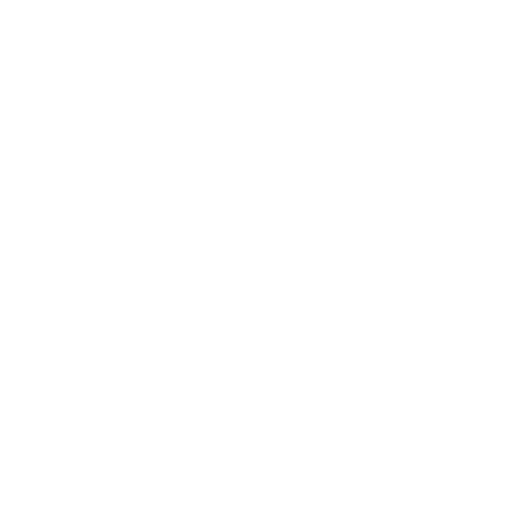夏の味覚として親しまれるトウモロコシは、その甘さとジューシーさで世界中の人々に愛される穀物です。しかし、その身近さとは対照的に、トウモロコシは数々の謎を秘めた植物でもあります。他の植物には見られない独特な繁殖方法を持ち、かつてはその起源が特定できず、「宇宙由来説」まで浮上したほどです。この記事では、トウモロコシの魅力に迫り、その起源の謎、世界各地への伝播の歴史、品種改良の軌跡、詳細な植物学的特徴、栽培のコツ、世界の生産と流通の現状、食料・非食料としての驚くほど多様な用途、そして栄養価まで、あらゆる側面から徹底的に解説します。この記事を通して、トウモロコシが単なる野菜や穀物ではなく、地球の歴史と人類の文化が色濃く反映された、奥深い存在であることを感じていただければ幸いです。
トウモロコシとは何か:多様な姿と世界における重要性
トウモロコシ(学名: Zea mays subsp. mays)は、イネ科の一年草であり、世界中で最も広く栽培されている穀物の一つです。その利用範囲は非常に広く、人間の食料、家畜の飼料としてだけでなく、工業用デンプン、植物油、バイオ燃料、さらにはプラスチックの原料としても重要な役割を果たしています。2009年の世界の年間生産量は8億1700万トンに達し、小麦、米と並び、世界三大穀物として世界の食糧安全保障に不可欠な存在です。特に日当たりの良い畑で栽培され、そのルーツは中南米にあります。15世紀末、クリストファー・コロンブスが新大陸を発見した際にヨーロッパに持ち込まれ、広まりました。日本へは16世紀末頃に伝わり、全国へと普及していきました。
「コーン」と「メイズ」:世界での呼び名の多様性
トウモロコシは一般的に「コーン」と呼ばれますが、この「corn」という言葉は、元々は穀物全体を指す言葉でした。しかし、現在のイギリスやカナダなど多くの地域では、特に指定がない限り、「corn」は主にトウモロコシを指す言葉として使われています。一方、学術的な場面や、英語圏以外の多くの国々、特にヨーロッパでは、トウモロコシを「メイズ」(maize)と呼ぶのが一般的です。これは、トウモロコシの原語である「マイース」(maíz)に由来しています。この呼び方の違いは、歴史的背景や地域ごとの穀物文化の違いを反映したものです。
日本では、地域によって「とうきび」や「トーキビ」、「なんば」、「もろこし」、「トウモロ」、「モロキビ」、「トウミギ」など、非常に多くの呼び名が存在します。『日本方言大辞典』には267種類もの呼び方が記録されており、その豊富さはトウモロコシが日本各地の生活に深く根付いてきたことを物語っています。一般的に使われる「トウモロコシ」という名前は、「トウ」が中国の王朝名である唐に由来し、「モロコシ」は唐土から伝わった植物であるモロコシ(タカキビ)に似ていたことから名付けられました。日本に伝来した当時、最も似ている植物がキビであったため、北海道から北関東では「とうきび」、西日本では「なんばんきび」とも呼ばれ、高麗(こうらい)または高麗黍と呼ぶ地域もあります。これらの名称はすべて、トウモロコシが外来植物であることを示しています。同様にヨーロッパでも、フランス語圏では「トルコ小麦」(blé de Turquie)、カナダのフランス語圏では「インド小麦」(blé d'Inde)、ドイツ語圏では「シチリア穀類」(grano siciliano)、イタリア語圏では「インド穀類」(grano d'India)など、「異国の穀物」を意味する様々な名前で呼ばれていました。中国での植物名は「玉米」(ぎょくべい)です。
トウモロコシの植物学的特徴と生育環境
トウモロコシは、中南米を原産地とし、高温で日当たりの良い環境でよく育つ大型のイネ科植物です。茎は一本で直立し、高さは2メートル近くまで成長します。葉は笹のように細長く、下部は鞘状になって茎を包み込みます。イネ科植物としては幅の広い葉を持ち、品種によって一生のうちに付く葉の数や丈の高さがほぼ決まっており、早生品種ほど丈が低く、葉の数も少ない傾向があります。熱帯原産の植物であるため、光合成経路としてC4回路を持つことが特徴で、これにより光を効率的に利用し、日当たりが良く、やや高温の環境を好みます。大型の作物であるため、生育期間中は10アールあたり350〜500ミリリットルの大量の水を必要とします。
自家受粉を避ける巧妙なメカニズム
トウモロコシは、一本の株に雄花と雌花が分かれて咲く、雌雄同株という特徴的な性質を持っています。しかし、その繁殖戦略は自家受粉を避け、異なる株との間で受粉を行うことで、遺伝的な多様性を維持しようとする傾向が強く見られます。種子が発芽してからおよそ3ヶ月後には、雄花と雌花がそれぞれの役割を担い始めます。雄花は、茎の先端から高く伸びる円錐状の花序に、無数の雄花だけをつけた小穂を密集させ、まるでキビの穂のような外観を呈します。一方、雌花は茎の下部の節にある葉の付け根から生じる円柱状の構造体で、全体が厚い包葉に覆われています。その先端からは、絹糸のような長い雌しべ(ひげ状の毛)だけが束になって外部へと伸び出します。この「トウモロコシのひげ」こそが、雌しべの重要な一部なのです。受粉が成功し、雌花のひげに花粉が付着すると、雌花の根元が膨らみ始め、私たちが食用とする実が形成されます。完全に成熟する頃には、ひげ状の雌しべは茶色く変色し、枯れていきます。イネ科の植物としては珍しく、種子が熟すと穎(えい)の中から顔を出すという特徴も持っています。種子の色もまた、黄色、白色、赤茶色、紫色、青色、濃青色など、非常に多様性に富んでいます。トウモロコシの食用部分は、子房ではなく実そのものであるため、実の形や性質の形成には、花粉親の影響が強く現れるという特徴があります。
栽培に適した環境と病害虫への対策
トウモロコシの栽培と繁殖は、日当たりの良い畑地を選び、春から夏にかけて種子を播種することで行われます。日本では、夏が旬の時期であり、6月から9月頃にかけて市場に出荷され、特に7月頃に最も多く流通します。日本のトウモロコシにとって最も注意すべき害虫は、アワノメイガです。この害虫は雄花に集まりやすいという習性があるため、人工授粉を行う際に雄花を取り除くことが、食害を減らす有効な対策となります。このように、トウモロコシの植物学的な特性と繁殖メカニズムを深く理解することで、より効率的で健全な栽培を実現することが可能となるのです。
謎に包まれたトウモロコシの起源と歴史
トウモロコシは、現代の私たちの食生活に欠かせない重要な作物ですが、その起源については、長い年月をかけて様々な謎と議論が繰り広げられてきました。その独特な生態は、他の多くの植物とは異なる特異な点が多く、まるで地球上の他の植物とは異なる「矛盾」を抱えているかのように見えたため、「宇宙から飛来した隕石に付着して地球にやってきた」という、SFのような「宇宙起源説」まで提唱されるほどでした。
長年の謎と「宇宙起源説」の登場
なぜ、このような突飛な説が生まれたのでしょうか。それは、長らくトウモロコシの原種を特定することができず、他の多くの身近な野菜や果物とは異なり、野生に自生していたとされる明確な「原種」が存在しないと考えられていたからです。さらに、トウモロコシは、繁殖のための種子が何重にも重なった厚い皮(包葉)に覆われているため、自然に任せて種子が地面に落ちても発芽しにくいという、種の繁栄という観点から見れば非合理的な特性を持っています。加えて、種子そのものが動物に食べられることで効率的に散布されるという、一般的な植物の戦略とも異なり、むしろ種子が動物に消費されることで次世代への命が繋がりにくい、とさえ指摘されてきました。これらの特徴から、トウモロコシは「種の繁栄のための本能」という生物が持つ基本的な概念に矛盾する、まるで動物に食べられるためだけに存在しているかのようだと言われ、地球上の植物の概念からかけ離れた特徴を持つ「謎の植物」とされてきたのです。
テオシント発見とDNA研究による検証
長きにわたり謎に包まれていたトウモロコシの起源ですが、近年のDNA研究の進展により、その解明が進んでいます。現在、最も有力視されているのは、中央アメリカに自生する野生種「テオシント」(Zea mays mexicana)がトウモロコシの原種であるという説です。かつては、絶滅した野生種とトリプサクム属、またはトリプサクム属とテオシントの交雑によって生まれたとする説もありましたが、遺伝子解析の結果、トリプサクム属を起源とする説は否定されています。テオシントとトウモロコシが分岐したのは約9200年前と推定され、紀元前5000年〜7000年前には既に食用としてのトウモロコシが存在していたと考えられています。原産地は中米地域とされていますが、単一の場所ではなく、中米の複数地域でそれぞれ品種改良が行われたという説が有力です。
テオシントと現代トウモロコシの相違点
テオシントは、現在のトウモロコシとは外観が大きく異なります。テオシントは枝分かれが多く、全体的に茂った印象ですが、トウモロコシは太い茎がまっすぐ伸び、葉が等間隔で生えています。雌穂も異なり、トウモロコシは100粒以上の実をつけますが、テオシントは5〜10粒程度と少なく、サイズも小さく、形状や色も異なります。さらに、テオシントの実はそのままでは食用に適しません。穎果(種子を包む殻)を見ると、トウモロコシの黄色い実は殻に覆われていませんが、テオシントの実は硬い殻に覆われています。また、テオシントは短日植物で、夏至から冬至の間に開花するのに対し、トウモロコシは日長に関係なく開花する中性植物です。このような形態や生態の違いから、テオシントがトウモロコシの原種であるという説は長い間疑問視されてきました。しかし、人類の長い年月をかけた試行錯誤により、わずかな実しかつけない野生種から、今日の豊かなトウモロコシが生まれたことは、人類の農業技術の偉大さを示す証拠と言えるでしょう。
新大陸文明を支えた主要食糧
トウモロコシは、発祥地である中米地域からメキシコ高地で多様化し、その後、メキシコ西部・北部から北米南西部を経て北米東部へ、またはメキシコ南部・東部からグアテマラ、カリブ海、南アメリカ低地へと伝播したと考えられています。南北アメリカ大陸では早い時期から主要な農作物となり、キヌアやアワなどの雑穀を除けば、唯一の主食となりうる穀物でした。アステカ、マヤ、インカといった古代文明では、トウモロコシが大規模に栽培され、これらの文明を支える基盤となっていました。特にアンデス地域では、ジャガイモなどの根菜類が主食でしたが、トウモロコシも重要な作物であり、宗教儀式や宴会で用いられる酒(チチャ)の原料として大量に消費されていました。インカ帝国では、段々畑を築き、トウモロコシの大量栽培を行っていたことが知られています。
旧世界への伝来と世界的な普及
トウモロコシが旧世界に伝わったのは、1492年にクリストファー・コロンブスが新大陸を発見した際、キューバでカリブ人が栽培していたトウモロコシを持ち帰ったのがきっかけとされています。ヨーロッパではすぐに栽培が始まり、1500年にはスペインのアンダルシア地方で栽培記録が残っています。最初に大規模な栽培が始まったのはオスマン帝国とされ、ヨーロッパでは「トルコ小麦」と呼ばれていました。珍しい植物であったトウモロコシは、当初は観賞用として扱われていましたが、食料としての小麦やライ麦に取って代わる形で急速に広まりました。16世紀半ばには地中海沿岸に広がり、16世紀末までにはフランス、ドイツ、イタリアにも拡大し、ヨーロッパ全土で栽培されるようになりました。ヨーロッパでは当初、貧困層の食料として受け入れられましたが、従来の穀物よりも圧倒的に高い収穫率は、「農業革命」によって増加した人口圧力を緩和する上で重要な役割を果たしました。また、「大航海時代」を迎えたヨーロッパ諸国の貿易船によって、トウモロコシは瞬く間に世界中に広がり、アフリカ大陸には16世紀に、インドには16世紀初頭に、そしてアジア東端の日本にも1579年に到達しました。この伝播は非常に速く、1652年にオランダ東インド会社がアフリカ南端のケープタウンに植民地を建設した際には、すでに現地のバントゥー系民族に陸路で伝わっていました。
アフリカでは急速に普及しましたが、19世紀まではソルガムやミレットなどの在来作物も多く栽培されていました。しかし19世紀後半以降、鉱山労働者の食料としての需要が増加し、労働者たちが契約期間を終えて村に戻った後もトウモロコシを好むようになったため、トウモロコシの栽培が拡大しました。さらに、トウモロコシはソルガムよりも生育期間が短いため、食糧が不足しがちな時期にも収穫することができました。そのため、特に南部アフリカや東アフリカにおいて、ソルガムからトウモロコシへの転換が進みました。ただし、トウモロコシはソルガムに比べて高温や乾燥に弱いため、サヘル地帯などの乾燥地域では、在来の雑穀を完全に駆逐するまでには至りませんでした。一般的にはコロンブスによって旧世界に持ち込まれたとされていますが、コロンブス以前の12世紀にアフリカ、13世紀にインドネシア(ジャワ島やスマトラ島)で栽培されていたとする研究もあります。古代ポリネシア人が太平洋を越えてアメリカ大陸の産物や技術をアフリカに伝えた際、トウモロコシもその中に含まれていたという説も提唱されています。
日本への伝播経路と利用の変遷
日本へトウモロコシが伝わったルートは、主に3つと考えられています。最も古いとされるのが「南西ルート」で、ヨーロッパ人が持ち込んだとされています。一説によると、1579年頃(安土桃山時代)、ポルトガル人が熱帯性の硬粒種(フリント種)を長崎に伝えたとされています。当時は、キビに似ていることから「トウモロコシ」の他に「南蛮黍(なんばんきび)」とも呼ばれ、漢字では黍、または玉蜀黍(玉は美しい、蜀は外国の意味)と表記されました。その後、稲作に適さない気候や水利条件の地域、例えば富士山麓や飛騨の山中、東北地方などに広がり、18世紀末には北海道のモロラン(現在の室蘭)にまで到達しました。しかし、当時は硬い硬粒種しか普及していなかったため、あくまで雑穀として扱われ、粥や餅に混ぜて量を増やすために使われることが多かったようです。江戸時代の農学者、宮崎安貞は『農業全書』(1697年)で、菓子の原料として利用できると記述しています。また、人見必大の料理書『本朝食鑑』(1697年)には、「火で炙って食べるか、乾燥させて粉にして餅にするのも良い」とあり、加工食品として消費されていたことがわかります。
日本でトウモロコシの栽培が本格化したのは明治時代以降です。明治初期に、近代的な育種法で作られたアメリカ産の早生デント種やフリント種が北海道に導入され、開拓使によって大規模な畑作が開始されました。これにより、トウモロコシは食用や飼料として普及し、やがて東北地方や関東地方にも広がりました。このルートは「北海道ルート」と呼ばれ、南西ルートと共に、日本への主要な伝播経路となりました。明治時代中期頃からは、東京の浅草(旧新吉原)の農家が始めた焼きトウモロコシの屋台が人気を博しました。さらに、1914年(大正3年)には「ゴールデンバンタム」が北海道で「黄金糯(こがねもち)」という品種名で優良品種として登録され、1929年(昭和4年)には日本食品製造合資会社の創業者が札幌市に缶詰工場を建設し、スイートコーンの缶詰製造を開始しました。
第二次世界大戦後の1953年(昭和28年)には、アメリカから新しいスイートコーンが導入され、野菜として未成熟なトウモロコシを栽培することが全国的に増加しました。育苗会社や農業試験場が世界中から種苗を取り寄せて開発した交雑品種が広く採用される事例が増え、このような導入経路は「自在ルート」と呼ばれています。1950年に開発された「ゴールデン・クロス・バンタム」がその代表例で、1953年に日本に導入され、缶詰用・生食用として広まりました。さらに1971年(昭和46年)には、サカタ種苗(現:サカタのタネ)がスーパースイート種「ハニーバンタム」を導入し、従来のものよりはるかに甘いトウモロコシが日本中に広がり、現代の生食文化の基礎を築きました。
多様なトウモロコシの品種とGMコーン
トウモロコシは、長い栽培の歴史の中で、食用、飼料用、工業用など、様々な用途に合わせて多くの品種や系統が開発されてきました。甘さや実の柔らかさ、風味などに重点を置いて品種改良が進められ、世界各地で様々な品種が作られています。異なる品種同士を交配させることで、その子どもの生育が旺盛になる「雑種強勢」を利用したハイブリッド品種が、20世紀初頭からアメリカで開発され、その後収量が飛躍的に増加しました。また、近年では遺伝子組み換え(GM)された品種も普及しています。
粒質による主要品種分類
一般的にトウモロコシの分類に使われるのは、粒の中のデンプンの構造によって種類を決定する「粒質区分」です。この粒質によって、用途や栽培方法に違いが生じます。
-
デント種(馬歯種): 粒の上部がへこんでいて、馬の歯のように見えることから名付けられました。デンプンが多く含まれており、主に家畜の飼料や工業用デンプンの原料として、世界で最も広く栽培されています。
-
フリント種(硬粒種): 粒が硬く、丸みを帯びています。ポップコーンの原料となるポップ種もこの一種です。穀粉や加工食品に使われ、日本で最初に導入された品種も硬粒種でした。
-
スイート種(甘味種): 糖度が高く、生で食べたり、缶詰や冷凍食品に使われる未熟な実を食べる品種です。スウィートコーンとは「甘いトウモロコシ」という意味で、甘味種全般を指します。ゴールデンバンタムやハニーバンタムなどが有名です。
-
ポップ種: 硬粒種の一種で、加熱すると内部の水分が蒸発して粒が膨らみ、ポップコーンになります。
-
ワキシー種(糯種): アミロペクチンだけで構成される、もち米のような粘り気のあるデンプンを持ち、食品加工や特殊な用途に用いられます。
-
ソフト種(軟粒種): 粒全体が柔らかいデンプン質で構成されており、粉末状にしやすい特徴があります。
遺伝子組換え(GM)コーンの現状
遺伝子組換え(Genetically Modified Organism; GMO)トウモロコシとは、特定の遺伝子を組み込むことで、害虫への抵抗性や除草剤への耐性などの特性を与えられたトウモロコシの総称です。これらのGMコーンは、特に世界の大規模農業において、生産効率の向上や農薬の使用量削減に貢献すると期待されています。トウモロコシの穀粒(袋詰め、サイロ、はしけ)や、粉砕加工品(コーングリッツ、コーンパウダー、コーンフラワー、コーンミールなど、穀粒を粉砕したもの)について、遺伝子組み換えの有無を検査する際には、トウモロコシ固有の遺伝子であるトウモロコシSSIIb(スターチシンターゼ IIb)との比較を行い、リアルタイムPCR法などの分子生物学的な手法を用いて定量検査が行われます。国際取引においては、意図せずに混入した組換え体の許容範囲は、大豆やトウモロコシについては5%以下を目安として取引が行われています。
日本においては、JAS分析試験ハンドブック『遺伝子組換え食品検査・分析法』や『安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法』の別添で規定されている系統が存在します。さらに、厚生労働省や農林水産省は「食用または飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬および廃棄、並びにこれらに付随する行為」の承認を継続しており、バイオセーフティークリアリングハウス(J-BCH)のウェブサイトに登録されているGMコーンは、2019年8月現在で112件(後代系統、使用期限切れを含む)に上ります。これらの承認されたGMコーンは、日本ではまだ商業栽培されていませんが、輸入された遺伝子組換えトウモロコシは、スーパーマーケットなどで一般的に販売されている植物性油脂、異性化糖、水飴、デンプン、コーンフレークなどの加工食品の原料として、日本国内で広く流通しています。日本では、表示義務の対象となるのはトウモロコシなど8種類の農産物と、それを原材料とする33種類の加工食品のみであり、上記の多くの加工品については表示義務がないため、消費者が意識せずに摂取している可能性があります。
原種トウモロコシの育て方:成功への道
原種トウモロコシの生育サイクルは、おおよそ4月中旬に始まり8月に終わります。春に種を蒔き、初夏から夏にかけて成長し、夏の盛りである7月から8月にかけて収穫期を迎えます。原種トウモロコシは、高い気温と十分な日照時間を好む植物で、理想的な生育温度は22〜30℃、種の発芽に適した温度は25〜30℃とされています。生育には高温が不可欠です。温度が低いと発芽しにくく、正常な受粉のためには12℃以上35℃以下の温度が望ましいです。耐霜性は低いですが、ビニール製のトンネルなどを使用することで苗を育てることが可能です。実を多く収穫するためには、雌花への十分な受粉が不可欠であり、畝を2列以上で設けると良いでしょう。栽培に適した土壌は、弱酸性で有機物を豊富に含み、深く耕せて水はけの良い畑です。根は病害虫に強く、野菜畑での輪作にも適しています。しかし、根は一度切れると再生しないため、植え替えには注意が必要です。肥料の吸収力は非常に高く、一般的な肥沃な畑でもよく育ちますが、特に食味の良い品種は生育が旺盛でない場合があるため、適切なタイミングでの追肥が重要になります。
受粉の重要性と品種の保護
原種トウモロコシは他家受粉をするため、受粉と受精がスムーズに進むように、同じ品種をまとめて栽培することが大切です。近くに飼料用などの異なる品種があると、花粉が飛散して交雑し、本来の品種特性が失われることがあります。そのため、同じ場所で栽培する場合は、1シーズンに1品種に限定するか、異なる品種を植える際は開花時期をずらす、または十分に距離を空けるなどの対策が必要です。
種まきから収穫までのステップ
種まきは4月中旬を目安に行います。根が深く伸びるため、元肥をしっかりと混ぜ込んだ畑を深く耕し、幅90cm以上の畝を立てます。畝にはマルチを敷き、地温を保ち、土壌の乾燥を防ぎます。1箇所に3〜4粒の種を、株間50cmの2列で30cm間隔で蒔き、2〜3cmの厚さで土を被せます。十分に水やりを行うと発芽が促進されます。発芽後、2回に分けて間引きを行い、最終的には草丈が10〜15cmになるまでに1箇所1本に整理します。間引きの際に丁寧に抜き取った苗は、別の場所に植え替えて育てることも可能です。苗から育てる場合は、育苗ポットに種を蒔き、本葉が3〜4枚になったら畑に植え付けます。
原種トウモロコシは肥料をよく吸収するため、生育が盛んな初夏の時期には特に多くの肥料が必要です。草丈が30〜40cmほどになったら、1回目の追肥を行います。また、倒伏を防ぐために、追肥と同時に株元に軽く土寄せをします。雄花が出始めた頃と、雌花が出始めた頃にも再度追肥を行うと良いでしょう。7月頃から1本の茎に数個の雌花がつきますが、実を大きく育てるために「芽かき」を行い、上の方にある1つまたは2つの雌花を残します。摘果した雌花は、ベビーコーンとして美味しく食べられます。出穂後の果実が肥大する時期は特に水分を必要とするため、水切れを起こさないように注意が必要です。雌花が受粉し、ひげが茶色に変わってきた頃(受粉後20〜25日程度)が収穫の目安です。原種トウモロコシは鮮度が落ちやすいので、食べる当日の早朝に収穫するのが理想的です。果実を触って実がしっかりと詰まっているのを確認し、根元から収穫します。
鳥獣害対策と病害虫の管理
原種トウモロコシの種子や発芽したばかりの芽は、鳥、特にカラスに食べられやすいです。そのため、種を直接畑に蒔く場合は被害を受けることがあります。鳥害を防ぐには、苗を育ててから植え付けるか、種を蒔いた後に不織布などを被せて保護する方法が効果的です。発芽が揃い、葉が緑色になったら、成長を妨げないように速やかに被覆材を取り外します。アワノメイガなどの害虫に対しては、雄穂を切り取って人工授粉を行うなどの対策が有効です。適切な管理を行うことで、品質の良い原種トウモロコシの収穫が期待できます。
世界と日本のトウモロコシ生産・流通・消費
日本で親しまれているトウモロコシは、甘みが特徴のスイートコーンが主流ですが、世界規模で見ると、家畜の飼料や工業製品の原料となるデントコーン(硬粒種)の栽培が大部分を占めています。飼料やデンプン、油の原料となるデントコーンやワキシーコーンといった品種は、その大半を輸入に頼っているのが現状です。
世界の生産量と主要生産国・輸出国
2017年における世界のトウモロコシ生産量は、約11億6440万トンに達しました。その中でもアメリカ合衆国が3億9760万トン以上を生産し、世界の総生産量の3割以上を占める最大の生産国です。2010年から2019年までの10年間で見ると、アメリカ合衆国、中国、ブラジル、アルゼンチン、インドが生産量上位5カ国となっています。国際的な取引においては、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ブラジル、ウクライナ、フランスが輸出国の上位を占めており、アメリカ合衆国は世界最大の輸出国として、全体の約3割のシェアを誇ります。そのため、アメリカの主要な生産地域の気候変動は、世界の在庫量や価格に大きな影響を与え、シカゴ商品取引所(CBOT)での国際的な投機の対象となっています。日本でも東京商品取引所において取り扱いがあります。一方、輸入国の上位5カ国は日本、メキシコ、韓国、EU、エジプトです。中国は世界第2位の生産国でありながら、国内の需要を満たせておらず、近年輸入量が増加傾向にあり、2019年には497万トンを輸入しています。
ハイブリッド品種とアグリビジネスの発展
近年、病害虫への抵抗力を高めるために遺伝子組み換え技術を用いた品種が世界中で普及しています。トウモロコシは雑種強勢という性質を持ち、これを利用したハイブリッド品種の開発により、収穫量が大幅に向上しました。しかし、ハイブリッド品種は一代限りの雑種であるため、農家は収穫した種を翌年の栽培に使用することができず、種苗会社から毎年購入する必要があります。この仕組みにより、種苗会社は安定した収益を上げることが可能となり、アグリビジネスが大規模化する要因となりました。20世紀中頃には、品種改良されたハイブリッド品種による収量増加が先進国から発展途上国へと広がり、「緑の革命」を推進しました。この結果、トウモロコシの生産量は増加しましたが、新品種の開発は飼料用トウモロコシが中心であり、人が直接食べる主食用のトウモロコシの進歩は緩やかでした。そのため、トウモロコシを主食とするメキシコやアフリカ諸国では、トウモロコシの生産性が十分に向上していないという問題も存在します。21世紀に入り、収量の向上だけでなく、発展途上国の人々に多いビタミンA欠乏症などの微量栄養素不足を解消するためのハイブリッド品種が開発され、ナイジェリアなどで導入が試みられています。
日本における輸入依存と国内生産の現状
日本はトウモロコシの大部分を輸入に頼っており、農林水産省や財務省の統計では、トウモロコシは「穀類」として分類され、そのほとんどが飼料として利用され、一部がデンプンや油脂の原料として加工されています。その輸入量は年間約1600万トンにも達し、これは日本の米の年間生産量の約2倍に相当します。日本は世界有数のトウモロコシ輸入国であり、その輸入量の約9割をアメリカ合衆国に依存しています。また、日本国内で消費されるトウモロコシの75%は家畜の飼料として使用されています。飼料用としては、粗飼料となる「青刈りトウモロコシ(コーンサイレージ)」や、濃厚飼料となる「子実を利用するトウモロコシ」が国内の酪農家などで生産されており、年間450万〜500万トン程度の収穫量がありますが、そのほとんどは自家消費されるため、市場にはほとんど流通せず、統計上は自給率0.0%とされています。
一方、未成熟な状態で収穫され、甘味種として一般的に販売され、家庭や飲食店で消費されるものは、統計上「スイートコーン」と呼ばれ、「野菜類(青果)」として分類されます。日本の年間スイートコーン国内生産量は25万〜30万トンに対し、生鮮スイートコーンの輸入量はわずかであり、店頭で販売される生食用スイートコーンはほぼ国産です。ただし、冷凍や加工されたスイートコーンの輸入量は9万トンから10万トン程度あります。平成22年度のスイートコーン国内総生産量は23万4700トンであり、都道府県別に見ると、最も生産量が多かったのは北海道(道内各地、特に十勝、上川地方)で10万7000トンに達し、国内総生産量の約40%を占めています。次いで生産量が多いのは、千葉県の1万6900トン、群馬県の1万4500トン、茨城県の1万0400トン、山梨県の9400トンの順となっています。国内で生産されるスイートコーンは、缶詰や冷凍食品の原料、またはそのまま食用として利用されます。前述の通り、輸入された遺伝子組み換えトウモロコシは、日本国内で商業栽培されていませんが、植物性油脂、異性化糖、水飴、デンプン、コーンフレークなど、表示義務のない加工食品の原料として広く使用されています。
世界における消費の実態:飼料用・工業用が中心、食用は限定的
2007年のトウモロコシの世界全体の消費構造を見ると、その大半は家畜の飼料として使われており、約64%を占めています。次いで、コーンスターチなどの工業製品の原料として約32%が利用され、人が直接食べる食用としての消費は、わずか4%に過ぎません。食用としての消費量は、国によって大きな差が見られます。例えば、アメリカや中国といった主要な生産国であっても、食用としての利用は比較的少ない傾向にあります。一方で、トルティーヤが食生活に欠かせないメキシコや、パップ、サザ、ウガリといったトウモロコシ粉を原料とする食品を主食とするアフリカ東部から南部にかけての地域では、食用としての消費が非常に大きいです。ただし、食用トウモロコシと飼料・工業用トウモロコシは品種が異なるため、飼料用トウモロコシの消費を減らして食用に転換することは容易ではありません(食用を飼料用や工業用に転用することは可能です)。過去にケニアで深刻な飢饉が発生した際、アメリカが食料支援としてトウモロコシ粉を提供しましたが、それがケニアでは食用としない黄色トウモロコシであったため、ケニア政府がアメリカからの支援を拒否した事例があります。これは、食文化や品種に対する理解の重要性を示す出来事です。
バイオエタノールの需要拡大と食料価格への影響
近年、最大の生産国であるアメリカにおいて、トウモロコシを原料とするバイオエタノールの需要が著しく増加しています。エタノール製造向けのトウモロコシ需要は、1998年の1300万トンから2007年には8100万トンにまで急増し、アメリカ国内のトウモロコシ需要の約3割を占めるようになりました。この需要拡大により、トウモロコシの需給バランスが変化し、従来の食用・飼料用需要との間で競合が生じた結果、価格が高騰し、2007年から2008年にかけての世界的な食料危機の一因になったとも言われています。さらに、バイオエタノール用のトウモロコシ栽培が増加したことで、大豆や小麦からの転作が進みましたが、トウモロコシはこれらの作物よりも多くの水を必要とするため、一部地域では水資源の不足が問題視されています。加えて、エタノールの市場価格とトウモロコシの市場価格の不均衡や、輸送インフラの未整備による採算性の悪化、エタノール燃料に対応した自動車の普及の遅れなどから、バイオマスエタノールの需要が伸び悩み、供給過剰によって生産されたエタノールの価格がガソリン価格の高騰にもかかわらず停滞しているといった課題も指摘されています。
トウモロコシの多様な用途:食料から工業原料まで
トウモロコシは、その実(果実)はもちろんのこと、茎、葉、芯、そしてひげに至るまで、植物全体があらゆる形で利用される、非常に用途の広い作物です。人間の食用としてだけでなく、家畜の飼料、工業製品の原料、さらには文化的な装飾品や薬としても活用されています。
食用としてのトウモロコシと健康への恩恵
トウモロコシの果実は、主食、野菜、加工食品の原料として非常に重要な役割を果たしています。乾燥させたトウモロコシは穀物として分類されます。野菜として利用されるのは、甘味種(スイートコーン)の未成熟な果実であり、旬は主に6月から9月ですが、鮮度の低下が非常に早く、収穫後1日経過するだけで味や栄養価が半減し、風味が損なわれてしまいます。そのため、収穫した日にすぐに茹でて食べるか、冷蔵保存する場合でも3〜4日程度で消費することが推奨されます。生のトウモロコシは、焼いたり、茹でたり、蒸したりと、素材本来の味をシンプルに楽しむ方法の他、サラダや和え物、炒め物、かき揚げなど、様々な料理に活用できます。加工品としては、粉食用のコーンミール、コーンフラワー、コーンスターチなどがあり、これらはパンや菓子、料理のとろみ付けなど、幅広い用途に使用されます。また、コーンパフなどのスナック菓子の原料としても広く用いられています。
歴史的な食用方法と世界各地の主食
トウモロコシは、栽培化が始まったメソアメリカにおいて、太古の昔から重要な食料源でした。乾燥させた種子は、石灰などを加えたアルカリ性の水で煮る処理(ニシュタマリゼーション)を経てすり潰され、「マサ」と呼ばれる生地となり、多様な料理に利用されました。代表的なものとしては、メキシコ料理の定番である、薄く焼いた無発酵パン「トルティーヤ」や、マサを様々な具材と共に植物の葉で包んで蒸した「タマル」が挙げられます。このアルカリ処理は、必須アミノ酸の一種であるトリプトファンが不足しがちなトウモロコシを主食とする地域において、ナイアシン欠乏症である「ペラグラ」を予防する効果があることが知られています。原産地であるメソアメリカでは、昔からこのアルカリ処理が行われていたため、ペラグラとは無縁でした。一方、アンデス地方の民族は、アルカリ処理をせずにトウモロコシを粒のまま煮て食べる習慣があります。この地域では、ジャガイモをはじめとする芋類が主要な作物であり、トウモロコシは煮て食べる以外に、発芽させたものを煮て糖化させ、発酵させて「チチャ」という酒にするのが一般的です。
古くから小麦粉などを製粉して利用してきたヨーロッパ、アジア、アフリカなどにトウモロコシが伝わると、同様に製粉して調理されるようになりました。アメリカ南部の「グリッツ」のように、水で練って焼くもの、イタリアの「ポレンタ」やルーマニアの「ママリガ」、南部アフリカの「パップ」や「サザ」のように、沸騰した湯の中で煮ながら練り上げ、粥状または固形状にするもの、中国の「ウォートウ」(窩頭)のように饅頭状にするものなどがあります。現代の日本では、このような主食としての利用はあまり一般的ではありませんが、かつては富士北麓地方など、米の収穫量が少ない寒冷地や山間部では、硬粒種のトウモロコシの完熟した粒をそのまま、あるいは粗く挽いたものを煮て粥にしたり、粉にして餅を作るなどして利用していました。南アフリカを中心とした南部アフリカでは、トウモロコシの粉を乾燥させた「コーンミール」を水や湯で溶かし、煮た「パップ」(pap)という、マッシュポテトのような、餅と粥の中間のような食感のものが、主に黒人層の主食となっています。パップはトウモロコシの成分が濃縮されており、7割以上が糖質であるため、これらの地域における肥満の一因ともなっています。わずかに発酵させたものはサワーパップと呼ばれます。
野菜としての利用と特殊な食材
未成熟な穂は、焼いたり茹でたりして野菜として食べられます。このような用途には、甘味種が用いられることが多いです。野菜として少し変わったものに、「ベビーコーン(ヤングコーン)」があります。これは、生食用甘味種の2番目の雌穂を若いうちに収穫して茹でたもので、サラダや煮込み料理などに使われます。さらに珍しいものとしては、メキシコでトウモロコシの黒穂病菌の一種である「ウスチラゴ・メイディス」菌(Ustilago maydis)に感染した穂(黒穂病)を「ウイトラコチェ(Huitlacoche)」と呼び、食用としています。その他、トウモロコシは様々な形で食材として利用されており、シチュー(西洋料理のコーンチャウダー、中華料理の玉米羹)、バターコーン、コーンサラダなどに加え、スナック菓子のコーンパフの原料としても広く使われています。
飲用としての利用
飲用としては、ビール、ウイスキー、バーボン、焼酎、ポン酒(コーン焼酎)など、様々なアルコール飲料の原料となります。また、焙煎したトウモロコシを煮出した「トウモロコシ茶」も人気があります。ペルーで作られる「チチャモラーダ」(スペイン語: chicha morada)というアルコールを含まないジュースは、紫色のトウモロコシから作られる伝統的な飲み物です。
トウモロコシの栄養価とペラグラの関係
トウモロコシは、主食として食べられるほど糖質が多く、野菜としてはカロリーが高めです。炭水化物、タンパク質、脂質をバランス良く含み、ビタミンB1、ビタミンE、食物繊維、ミネラル(カリウム、リン、鉄など)といった様々な栄養素も豊富です。トウモロコシの一粒一粒を覆っている外皮は、セルロースという不溶性食物繊維でできており、その含有量はゴボウの4倍にも相当します。この食物繊維は腸内環境を整え、老廃物や有害物質と結合して体外に排出する働きがあり、血管を健康に保ち、動脈硬化や大腸がんの予防に役立つと言われています。また、胚芽部分に含まれるリノール酸は、コレステロール値を下げ、動脈硬化の予防に効果があると考えられています。トウモロコシの黄色い色素はキサントフィルに由来し、血管を柔らかく保つ効果が期待できます。ただし、表皮は消化が悪いため、胃腸が弱い人は食べ過ぎると下痢を引き起こすことがあります。ビタミン類ではビタミンB1が豊富で、糖質をエネルギーに変える際に重要な役割を果たすことが知られています。野菜の中ではカリウムの含有量が多いのも特徴です。
しかし、トウモロコシの種実には、体内で合成できない必須アミノ酸であるトリプトファンが少ないという欠点があります。トリプトファンは、体内でビタミンB群の一種であるナイアシンに変換されます。そのため、昔からトウモロコシを主食としてきた南アメリカ、アメリカ南部、ヨーロッパの山間部、アフリカの一部などでは、ナイアシン欠乏症である「ペラグラ」(pellagra、別名イタリア癩病)が多発し、現在でもその状況が続いている地域があります。これは、トウモロコシを主食とする食文化圏が抱える深刻な健康問題の一つです。しかし、原産地であるメソアメリカでは、古来より前述のアルカリ処理(ニシュタマリゼーション)を行うことで、トリプトファンからナイアシンへの変換を促進し、欠乏症を予防してきたため、ペラグラとは無縁でした。この伝統的な処理方法がいかに科学的であったかを示す良い例と言えるでしょう。
食用以外の多様な利用法
トウモロコシは、食料として広く知られていますが、その利用範囲は食用にとどまらず、様々な部位が工業製品や文化的な用途に活用されています。
果実(種子・胚芽)の用途
トウモロコシの実は、人間が食する以外に、家畜の飼料として大量に消費されています。2007年の統計では、世界全体の消費量のうち、家畜飼料が64%、コーンスターチやコーン油などの工業用途が32%を占めています。その他、デンプン(コーンスターチ)、食用油(コーン油)、異性化糖(コーンシロップ)の原料となるだけでなく、コイやフナ釣りの餌としても利用されています。
トウモロコシは、純度の高いデンプンを効率的に抽出できるため、工業原料として重要な役割を果たしています。胚乳から得られるデンプンは、紙、繊維、接着剤の製造に用いられるほか、発酵させることでエタノール、アミノ酸、プラスチックなど、多様な化学物質に変換されます。こうして生成された異性化糖は、甘味料として広く利用されています。近年では、地球温暖化対策やエネルギー安全保障の観点から、再生可能エネルギーであるバイオマスエタノールやバイオプラスチックとしての利用が拡大しており、自動車燃料などへの応用が進んでいます。特にアメリカでは、バイオマスエタノールの原料としての需要が高まり、価格が高騰し、2008年には国内需要の3割を占めるに至り、大豆や小麦からの転作も増加しました。また、ドイツでは、飼料用トウモロコシの実を加工したペレットを用いた暖房用ストーブが「コーンストーブ(Maistofen)」として製造・販売されています。
その他、トウモロコシの果実は、胃腸の調子を整える効果があるとして「玉蜀黍(ぎょくしょくしょ)」という生薬としても利用され、茹でて食されます。胚芽から抽出される脂肪油は、医薬品の溶剤や軟膏の基剤として使用されることがあります。文化的な用途としては、「インディアンコーン」と呼ばれる色鮮やかなトウモロコシの種が、北米の先住民の間で感謝祭や収穫の時期に、ドアやテーブルを飾る風習があります。
軸(コブ)の用途
実を取り除いた後の軸(コブ)も、様々な方法で有効活用されています。合板、紙の原料、研磨剤、飼料、吸着剤(油吸着材など)の製造原料として利用されるほか、粉砕した粉末は「コーンコブ」と呼ばれ、培地の原料や床材として用いられます。芯が柔らかく円筒形に加工しやすい特性から、喫煙具である「コーンパイプ」の主要な材料としても利用されています。第二次世界大戦後、日本の占領軍総司令官を務めたダグラス・マッカーサー元帥が、コーンパイプを手にした姿がよく知られています。現在のコーンパイプは、1946年に芯の利用を目的として開発された専用品種を材料として製造されています。
茎・葉の用途
茎や葉は、家畜の飼料や土壌に混ぜ込む緑肥の材料として活用されており、そのために栽培される青刈りトウモロコシも存在します。収穫後に放置して枯れた茎や葉を裁断し、土に混ぜ込んで肥料として利用することもできます。種子が硬く色鮮やかなトウモロコシは、包葉を取り除くかバナナの皮のように剥いて乾燥させ、観賞用として利用されます。取り除いた包葉は、繊維や布の代わりとして用いられることもあります(包葉を使ったバスケットなど)。日本では、新潟県を中心に、1947年頃からトウモロコシの皮(きみがら)を材料とした「きみがら細工」が作られ、県の伝統工芸品となっています。
花柱(ひげ)の薬効
雌花のめしべから伸びる花柱、一般的に「ひげ」と呼ばれる部分が、茶褐色に変化し乾燥した状態になったものを採取し、天日で乾燥させると、生薬としての価値を持ちます。これは「玉蜀黍蕊(ぎょくしょくしょずい)」、または「玉米鬚(ぎょくべいしゅ)」という名で呼ばれ、日本国内では「南蛮毛(なんばんもく)」という名称で流通しています。特に注目されるのはその利尿作用です。この利尿効果は、南蛮毛に豊富に含まれるカリウムによるもので、体内の過剰な塩分と結合して体外へ排出を促すため、むくみの解消や血圧の安定に寄与すると考えられています。副作用のリスクが低く、お茶(南蛮毛茶)としても親しまれています。南蛮毛は、初期の『日本薬局方』に掲載されていた利尿薬「サリチル酸ナトリウム」の代替品として研究された歴史があります。中国伝統医学においては、利尿作用のほか、急性腎炎、妊娠中のむくみ、脚気に対して、蕊(ひげ状の部分)を5〜10グラム用い、300〜600ミリリットルの水で煮出して、1日に3回に分けて服用する方法が伝えられています。近年の中国における研究では、血糖値を下げる作用、胆汁の分泌を促進する作用、止血作用なども確認されており、これらの効果を活用するため、糖尿病や高血圧、慢性胆嚢炎の治療薬としても用いられています。ひげの数は実の数と直接関係しており、ひげが多いほど実がぎっしりと詰まっており、色が濃い茶色であるほど成熟が進んでいると判断できます。
まとめ
トウモロコシは、その起源が長きにわたり謎に包まれ、「宇宙起源説」まで浮上するほど特異な存在でしたが、およそ9200年前、テオシントという原種から、人類による長い年月をかけた品種改良を経て、今日の姿へと進化を遂げました。中南米の古代文明を支える重要な食料として発展し、大航海時代を通じて世界各地へと広まりました。日本へは16世紀末に伝来し、現在では主に北海道を中心に栽培される、私たちにとって身近な作物となっています。その植物学的な特徴、多様な品種、特に遺伝子組み換え(GM)品種の普及と流通は、現代農業における重要な要素となっています。 栽培においては、高温で日照時間が長い環境を好み、適切な土壌管理、施肥、水やり、そして受粉を促進する対策が、豊かな収穫を得るための鍵となります。世界全体で年間11億トン以上が生産されており、アメリカ合衆国が主要な生産国および輸出国である一方、日本は世界有数の輸入国として、飼料用を中心に大量のトウモロコシを消費しています。食用としては、スイートコーンの未熟な実が野菜として人気を集め、メソアメリカのトルティーヤやアフリカのパップなど、世界各地の食文化を支える主要な食材となっています。また、高い栄養価を持つ一方で、必須アミノ酸のバランスが偏っているため、ペラグラを発症するリスクがあることも知られています。食料としての利用以外にも、デンプン、油、バイオ燃料、プラスチック、さらには医薬品や工芸品など、その用途は非常に多岐にわたります。 トウモロコシは、地球の歴史、人類の文化、そして科学技術の進歩を反映する、まさに「生命の神秘」を秘めた作物と言えるでしょう。その全体像を深く理解することは、食料問題、環境問題、そして持続可能な社会の実現に向けた考察において、非常に重要な視点を与えてくれます。
質問:トウモロコシの原種は何ですか?
回答:トウモロコシの起源は長い間不明でしたが、近年のDNA研究によって、中央アメリカに自生するイネ科の野生植物「テオシント」(学名:Zea mays mexicana、別名:ブタモロコシ)が、最も可能性の高い原種であると考えられています。テオシントから現在のトウモロコシへと進化したのは、およそ9200年前と推定されています。
質問:トウモロコシの名前の由来は何ですか?
回答:日本語における「トウモロコシ」という名前は、「トウ」が中国の王朝名である「唐」に由来し、「モロコシ」は中国から伝来した植物である「モロコシ」(タカキビ)に似ていることから名付けられたとされています。また、日本各地では「トウキビ」や「ナンバンキビ」など、さまざまな呼び名で親しまれています。
質問:日本のトウモロコシ栽培は、いつ、どのような形で始まったのでしょうか?
回答:日本におけるトウモロコシの歴史は、大きく分けて3つのルートで語ることができます。最初に到来したのは「南西ルート」で、安土桃山時代の1579年頃、ポルトガル人が硬粒種と呼ばれる種類のトウモロコシを長崎に持ち込んだと伝えられています。次に、「北海道ルート」として、明治時代にアメリカから導入された品種が北海道で大規模に栽培されるようになりました。そして、戦後になって甘みの強いスイートコーンが広まった「自在ルート」へと続いていきます。